まず最初に。
ロードバイクに気付きベルを付けることに反対派(?)の私。
あえて気付きベルを紹介します。
鈴丸
東京ベル(TOKYO BELL) ベル 鈴丸(suzumaru) シルバー TB-SZ1
これは動画を見てもらったほうが早いと思います。
要はハンドルに装着し、走行振動で揺れて鳴る気付きベルの一種と考えればいい。
あえてこれを書いた理由なんですが、ON/OFFの切り替えが可能だという点。
道交法では、ベルを鳴らさないといけない場面と、鳴らしてはいけない場面を規定しています。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
実際のところ、警音器鳴らせの標識があるようなところって、コーナーリングの連続だったりします。
ロードバイクで鳴らせと言われても、そんな場面でハンドルから手を離すのは怖く、ハンドル操作とブレーキングが優先する。
なのでそういう区間でONにしておけば解決する・・・と言いたいところなんですが、警音器と呼べるほどの音量ではなさそうw
ただまあ、一瞬でOFF⇒ONに変えて、さらにハンドル操作できる(勝手に鳴っている)という点では、ある意味では需要があるのかもしれません。
まあ、こんなものもあるよということで。
歩行者目線
冒頭で、
ロードバイクに気付きベルを付けることに反対派(?)
と書いたのですが、歩行者目線で見たときに、気付きベルを付けていてくれたほうがありがたいと思う人もいるようです。


たぶん使い方の問題だと思うのですが、例えばサイクリングロードで歩行者がいても減速せずに、時速35キロ以上でガンガン走っている。
気付きベルを使うことでドケドケ効果を狙っているというなら、アウト。
歩行者がいれば減速するし、相手に分かりやすくするために使うならそこまで悪いものとも思えません。
ただし、威嚇されたと感じる人もいてトラブルになる可能性もあるので、個人的にはさほどオススメしません。
そういうところまで考えて、標識でベルを鳴らす必要があるけどブレーキングをおろそかにしたくない、という人には、標識の手前で鈴丸をONにして勝手に鳴らせておく。
それ以外は極力OFFにするという運用もできなくはないかと。
ただしレビューを見る限り、いわゆるベルよりも音量が小さいようなので、そこまで考えるとさほど魅力的とも言えませんが、誰かうまい有効活用が出来る人もいるかもしれないので一応お知らせという記事です。
というよりも、歩道を低速で走るおじいちゃんが乗る自転車とかだと、むしろこういうのを付けておいたほうがいいと思ってます。
理論上は歩行者優先で、歩行者がいれば自転車は徐行や停止などをして歩行者を妨害してはいけないルール。
だけど小さな子供連れの親からしたら、ブレーキングとか期待できそうもない爺さんの自転車の存在をいち早く知ったほうが、子供を守れる。
それこそ、子供がパッと手を離して歩道上で変な方向に動いた時に、爺さんの低速自転車が転倒する可能性もある。
そういうとき、責任問題にもなりうるので、それならいち早く爺さんの自転車の存在に気が付いたほうがいいという見方も成り立つ。
本来のルールで言えば歩行者優先は間違いないにしろ、むしろ高齢者が乗る低速自転車にはこういうを付けていたほうが、歩行者も高齢者もお互いにハッピーなのかもしれません。
東京ベル(TOKYO BELL) ベル 鈴丸(suzumaru) シルバー TB-SZ1
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


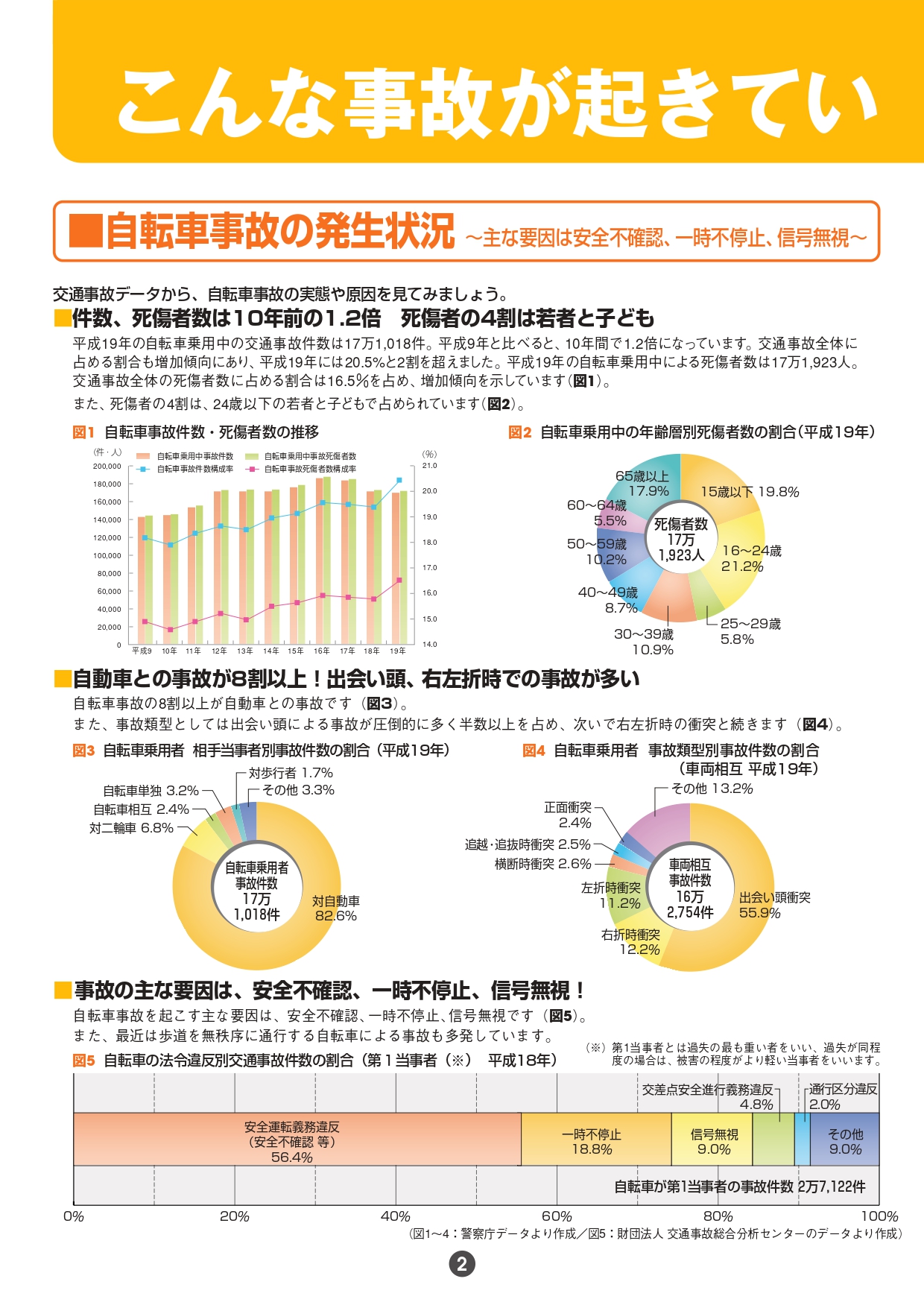

コメント