先日書いた記事。

こんにちは
これ系ですと個人的にはコーナー内のハンプが苦手です
たぶん走り屋対策とかだと思うんですが、特に下りだと跳ねてトラクションが抜けるので、コーナーの走行ラインや制動距離が読みづらい…
速度抑制が目的ならコーナー手前に設置したほうが効果的だと思うのですが
海外のロードレースを見ていると市街地に大き目のハンプは良く見られますが、山道にはあまりないようですね
たぶん、これのもうちょっとハンプが高めの奴のことですよね??

確かに
確かに、下りコーナーリングの手前で減速させたほうが理にかなっている気もするのですが、直線部分にこれがあっても、さほど減速してくれないとかそういう事情もあるのかもしれません。
真っ先に頭に浮かんだの、多摩川サイクリングロードのハンプ。

これ、調布とか府中のあたりにはあるのですが、これがあるのは理由があって、昔暴走自転車が歩行者に衝突して死亡事故を起こしているからです。
多摩サイって歩行者も多いですし、小さい子供もうろうろしているのですが、そんな中でもかっ飛ばす自転車勢がいますから。
とは言っても、あまり高いハンプは作れないらしい。
というのも、例えば車椅子の方が散策しているとか、足が不自由な方も歩いているわけで、自転車の減速だけを考えて作ると違う問題が出てしまう。
跳ねてトラクションが抜けるのって、ロードバイクは最悪ですからねぇ・・・
十分減速していないと、ハンプ+下り+コーナーリングは爆死するので、減速させるという意味ではそれなりに効果があるのかも。
個人的にはこっちのほうが嫌いなんですが、

もっと嫌いなのは、謎の縦筋が入っているところ。
タイヤを持っていかれそうで怖い。
下りコーナーは十分な減速と視線で
峠を下っていると、なんかおかしなライン取りしているなぁと思うロードバイクもそこそこいて、左コーナーで中央線付近までせり出しているのとか見ます。
減速が不十分なのと、体勢が高すぎることでうまく曲がれていないことが原因だと思うのですが・・・
峠道で怖いのって、バスなんですよ。
道が狭い峠道って、バスが曲がるにはセンターラインを越えざるを得ない。
内輪差の問題で超えるのもありますが、あれはそもそもしょうがない。
峠の走り方で、センターラインを越えていなくても、事故の原因としてキープレフト違反(18条1項)で過失とした判例もありました。
平成27年8月26日東京高裁の判例ですが、センターラインの左側70センチのところを通行していたオートバイが、大型車と衝突した事故。
大型車が曲がるにはどうしてもセンターラインを越えるので、キープレフト走行していれば事故が起きなかったとして、オートバイ側の過失を認めています。
センターラインオーバーの場合、基本的には0:100でラインオーバーした側に過失があるわけですが、峠道など狭い道路では必ずしもそうはなりません。
コーナーの前には十分減速することと、下ハンドルを持って体勢を低くし曲がりやすくする。
視線をコーナーの出口に向けて曲がる。
こういうことをしっかりしていないと、センターラインを越えたり、センターライン付近までせり出してしまう。
といっても、こういう減速帯がある場所だと、



相当減速していないと、下手すると吹っ飛びますし。
あんまり好きではない道路構造ですが、かっ飛ばす奴がいるから事故防止のためにあるので、しょうがない。
下ハンドルって持たない??
峠の下りでもブラケットのままのロードバイクってそれなりに見かけますが、怖くないんですかね?
個人的にはとっても不思議。

下ハンドルを使いこなすには、レバーの位置なども下ハンでも使いやすいようにきっちり調整しておくことが大切。
ショップだと、とりあえずはブラケットで使いやすいようにしかセッティングしませんし。
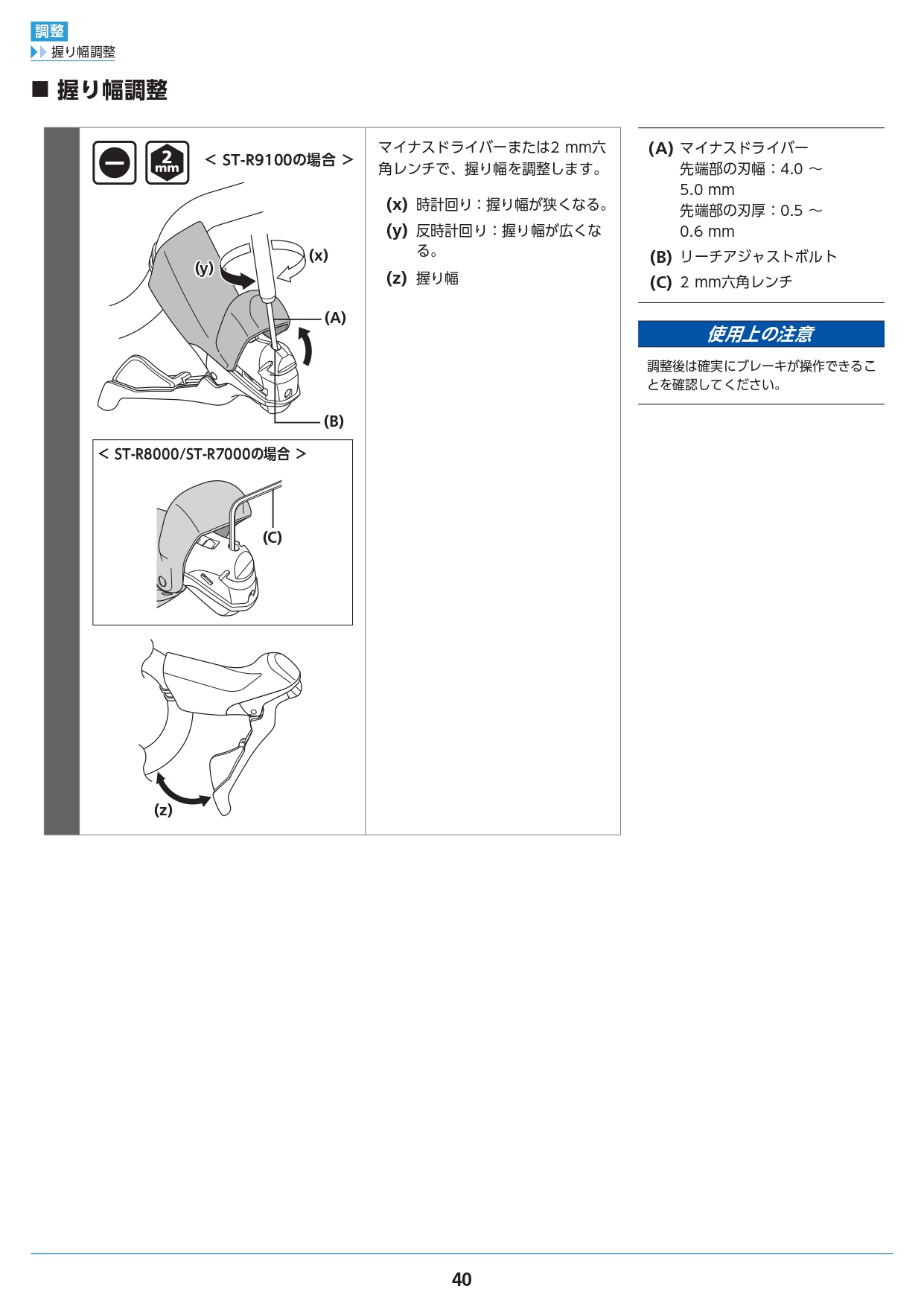
慣れてないのに下ハンドルでブレーキングすると、思っている以上に制動が掛かって吹っ飛ぶ人もいるので、こういうのも軽めの斜面から練習するしかないんですけどね。
ブラインドコーナーは何があるかわからないので、甘く見ずにきっちり減速することが大切。
ご意見ありがとうございました。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント