こちらの記事にご意見を頂きました。

この大阪の事故の翌日(7月7日)、もっとひどい事故が東京で起こってましたが、報道は7月11日でした。
大阪の事故が霞むほど、ひどい内容です。(けが人無しで幸いでした)
【引用:6日昼ごろから都内の居酒屋などでビールやハイボールなど計16杯程度、飲酒。午後11時ごろ、新宿区内からシェアリングサービスの電動キックボードに乗り】
ビールやハイボール16杯も飲んで、よく乗ろうと思ったもんです。
大学生は19歳だったとのことなので、居酒屋への同行者がいたら、飲ましても、乗らせても、何か罰則が有るのでは無いかと思います。
あと、年齢確認しなかった居酒屋も。
こんなのがいると思うと、夜中に家の近所を歩くのも危険なことになりそうです。
個人的な感想としては。
Contents
もったいない

個人的な感想としては「もったいない」でして、昨年飲酒運転の末に転倒して死亡事故が起きたときから何度も書いてますが、

特定小型原付なんて、今までの実証実験の流れからしても問題が起きる度にマスコミやインターネットが騒ぐことは予見可能なわけで、既存のモビリティよりもクリーンであることを証明するためにもアルコールチェッカーを組み入れるくらいがちょうど良かったのよね。
しかも今まで存在しなかった新しいカテゴリーとして作ったわけで、流通する以前に保安基準に入れるのがベターでした。
今さらクルマに対して「アルコールチェッカー義務付け」しても、新車限定にするか一定の猶予期間を設けないと厳しい。
新しく作ったカテゴリーなんだから、最初に組み込んでしまえば少なくとも酒に関しては他のモビリティよりも「クリーン」なんだとアピールできたわけでして。
ちなみに令和4年の飲酒運転による事故件数(全ての車両)は2167件、1日あたり約5.94件です。
令和3年の飲酒運転検挙数は約2万件(1日あたり約54.8件)ですが、免許持ちの人たちですらこんな有り様なんだから、なおさらアルコールチェッカーで物理的に動きを封じるべきだったとしか。
刑罰を重くしても、「バレなきゃOKマン」が必ずいることは歴史が証明しちゃっているのだから。
事業者向け指針としては
警察庁の有識者会議(パーソナルモビリティ安全利用官民協議会)の2023年3月7日では、一応シェアリング事業者向けガイドラインが出ています。
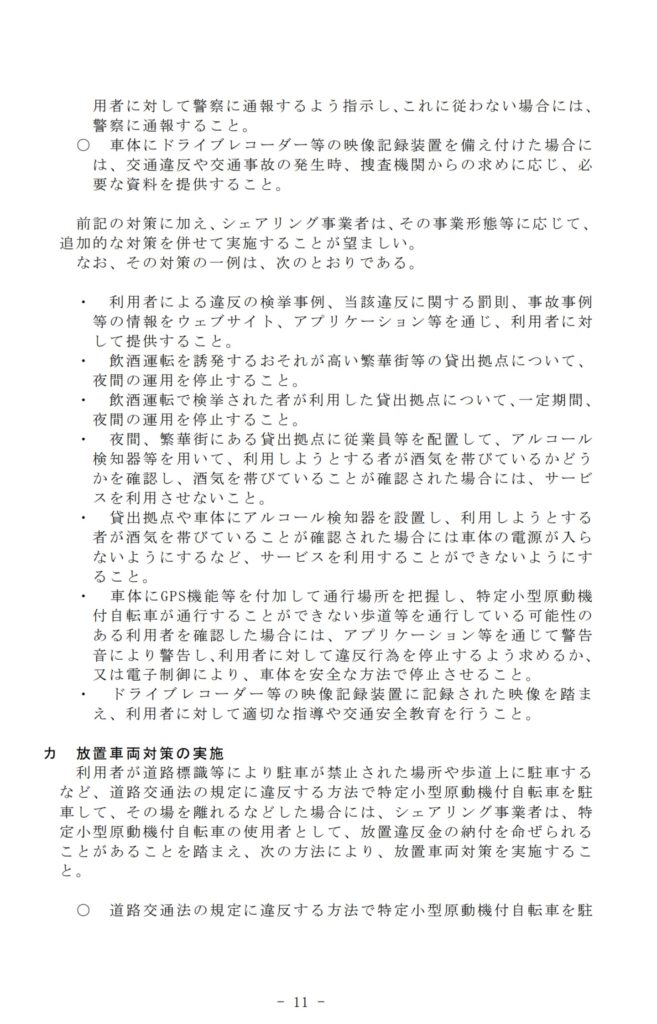
前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。
なお、その対策の一例は、次のとおりである。
・ 利用者による違反の検挙事例、当該違反に関する罰則、事故事例等の情報をウェブサイト、アプリケーション等を通じ、利用者に対して提供すること。
・ 飲酒運転を誘発するおそれが高い繁華街等の貸出拠点について、夜間の運用を停止すること。
・ 飲酒運転で検挙された者が利用した貸出拠点について、一定期間、夜間の運用を停止すること。
・ 夜間、繁華街にある貸出拠点に従業員等を配置して、アルコール検知器等を用いて、利用しようとする者が酒気を帯びているかどうかを確認し、酒気を帯びていることが確認された場合には、サービスを利用させないこと。
・ 貸出拠点や車体にアルコール検知器を設置し、利用しようとする者が酒気を帯びていることが確認された場合には車体の電源が入らないようにするなど、サービスを利用することができないようにすること。
・ 車体に GPS機能等を付加して通行場所を把握し、特定小型原動機付自転車が通行することができない歩道等を通行している可能性のある利用者を確認した場合には、アプリケーション等を通じて警告音により警告し、利用者に対して違反行為を停止するよう求めるか、又は電子制御により、車体を安全な方法で停止させること。
・ ドライブレコーダー等の映像記録装置に記録された映像を踏まえ、利用者に対して適切な指導や交通安全教育を行うこと。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/newmobility0503.pdf
ガイドラインという形ではこうなってますが、
貸出拠点や車体にアルコール検知器を設置し、利用しようとする者が酒気を帯びていることが確認された場合には車体の電源が入らないようにするなど、サービスを利用することができないようにすること
どうせ飲酒運転事故が起きてマスコミが騒いで叩かれる構図になるだけなんだし、いち早くこのようなシステムを組み入れるべきだったとしか。
なので私の感想としては「もったいない」です。
免許持ちだろうと飲酒運転するし、バレなきゃOKマンなんてそこら辺にウヨウヨしているのだから、物理的に封じない限りは厳しい。
既存のモビリティよりもアルコールに関してはクリーンなんですよとアピールできるチャンスを逃したとも言えますが、アルコールチェッカーと電源を同期するシステムを早く構築することが望まれます。
特定小型原付を叩きたい勢なんていくらでもいるわけで、対策は「やり過ぎ」なんじゃないかくらいがちょうどいいのですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/COIY76VBNRPYNBG35QPQTP3RDA.jpg)


コメント
レンタルやシェアだと、すぐに変更できそうですね。
しかし、警察庁のガイドラインで、「望ましい」とされていたのに、付けていないと言うことは、シェア事業者は、「飲酒運転やむなし」と考えているのでしょう。
すぐ変更できるから、問題があれば付けたら良いや、的な感じかと思います。
コメントありがとうございます。
どこまで検討しているかはわかりませんが、仮にアルコールチェッカーを搭載した場合に、アルコールチェッカー上は問題無しだけど飲酒検問で引っ掛かるみたいな事態が出たら事業者責任になるのかなと思ったりします。
なのできちんとアルコールチェッカーの基準を定めないとまずいのかもしれません。
ああ、確かに。
アルコールチェッカーの精度や事業者責任の問題はありますね。
事業者の責任を無くすか減らすかしないと、永遠に付かないですね。
しかし、原付でスピード違反しても、速度リミッターがあるのに違反したのは、メーカーが悪い、とは言わないので、(60km/hまで出るからですが)、そのへんの責任は、使用者に求めるべきかと思います。
コメントありがとうございます。
個人的にはガイドラインではなく義務付けして欲しかったのですが、今後に期待していいのかはわかりません笑。
だいぶ費用が掛かる話とは言え、何かしらシステム開発中と信じたいですが。