冬場になるとやたらとペダリングが重く感じてしまうことってないですか?
真夏に比べるとやたらと抵抗を感じるというか、遅く感じてしまいます。
これは実際のところ、空気自体が重たいのです。
空気の重さ

空気自体にも、当たり前ですが重量があります。
空気は様々な気体の混合物でして、8割くらいは窒素、2割くらいは酸素と言われています。
さらに水蒸気を空気中に含んでいるわけです。
これはいわゆる湿度とも関係しますね。
夏と冬でなぜ空気の質量が変化するのかという話ですが、これは空気中にある【乾燥空気量】と【水蒸気量】が関係します。
空気中の乾燥空気量と水蒸気量だと、根本的に乾燥空気量のほうが多いわけです。
夏場と冬場ではこのようになります。
・夏場
乾燥空気量 ⇒ 冬場よりも減少
水蒸気量 ⇒ 冬場よりも増加
・冬場
乾燥空気量 ⇒ 夏場よりも増加
水蒸気量 ⇒ 夏場よりも減少
絶対的な量は、乾燥空気量>水蒸気量 となるので、空気の重さとしては冬場のほうが重量が増加するわけです。
そして乾燥空気量が大きいほど空気の密度は濃いという形になります。
空気抵抗

空気抵抗の詳しい計算式はあえて書きませんが、前面投影面積、空気の密度、速度に比例します。
前面投影面積というのは、要はデカいもの(面積が大きいもの)にすれば空気抵抗は増えるという理屈。
速度が上がれば空気抵抗が増すというのはロードバイク乗りなら誰でも経験していることです。
ここで大切なのは、空気の密度にも比例するんですね。
なので空気の密度が濃い冬場のほうが、空気抵抗が大きくなるというわけです。
冬場はウェアも重い
(パールイズミ)PEARL IZUMI 3500BL サイクルジャケット ウィンドブレーク ジャケット[メンズ] 3500BL 3 カーマイン 3 L
冬は寒いので、必然的にウェアも重くなります。
これもなかなか無視できないくらいの重量です。
これも【冬場はペダリングが重い】と思わせる要因でしょう。
冬場は筋肉も硬い

冬は寒いので結構も悪くなり、筋肉も硬くなりがちです。
ロードバイクを動かすには筋肉が必要ですので、筋肉が温まっていなくて硬化しているとペダリングが重いのも当然です。
冬場は気持ちも重い

寒い日って、外に出るまで時間がかかったりしますよね。
気分的なものと言ってしまえばその通りですが、気持ちの重さはペダリングの重さにもつながります。
様々な要素で冬場は【重い】

一番大きな要素は空気抵抗が増えるということですが、冬場にペダリングが重く感じるとか、前に進まない感じがするのは当然のことです。
これは物理学的に、計算すれば出せる数字です。
私自身、冬場は平均速度が1キロくらい落ちていたりします。
体感的には空気が重いと感じますが、これはちゃんと理由があって冬場は空気抵抗が大きいということが挙げられます。
これに対する対抗策ですが、正直なところでいうとありません。
自然を相手に闘うのがロードバイクですので、すべての人間に同じように負荷がかかるのが冬場の重さです。
これに付随して書きますが、ローラー台ばかりやっている人は、やり方を間違うと下手になると思っています。
ローラー台では空気抵抗がかかりませんので、実走とは違うのです。
先日コメントいただいた方も、ローラー台で速くなる乗り方を覚えてしまったみたいに書かれていましたが、ローラー台は所詮はローラー台です。
冬場は地域によっては外を走ることが困難ですが、速くなりたいなら外を走ったほうが効果的です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

![(パールイズミ)PEARL IZUMI 3500BL サイクルジャケット ウィンドブレーク ジャケット[メンズ] 3500BL 3 カーマイン 3 L](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41rqiqeo08L.jpg)
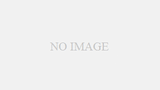

コメント
今更のコメントで済みません。この記事はいつになくアッサリし過ぎてませんか?
冬場の空気抵抗増加の原因(水蒸気量の低下、気温低下による密度増加)を感覚的に書かれている印象を強く受けてしまいます。いつもなら「数値的にどの程度増加する」とか、もっと掘り下げておられると思うのですが…
大気の8割を占める窒素の分子量は28で残り2割を占める酸素の分子量は32。よって大気の平均分子量は28.8。一方、水蒸気(=水)の分子量はそれより軽い18なので、湿度が高い(大気中に水蒸気の割合が多い)ほど大気は軽く空気抵抗が少なくなる。
具体的数値を考えてみると、夏場を気温30℃湿度80%と仮定し、冬場を気温・・・・・
コメントありがとうございます。
詳しい時系列を思い出せないのですが、元々はこんな感じで細かい数字などは上げずに書いてました。
読み手の層も様々なので、理系的な話になると敬遠する方もいると思ってのことなのですが、あるときにもっと詳しく理論的なことなど書くべきとクレームを受けまして、そこから軌道修正しているということもありまして。
いまだにどっちが読み手に取っていいのかは、正直わかりません。
resありがとうございます。
理論的には「影響がある」のは間違いないとしても、その影響が測定誤差範囲内とかで無視できるレベルなのかとかは気になっちゃいます。それは理系文系にはよらないと思います。私は詳しく書いてくださっている今のスタイルが好きです。
コメントありがとうございます。
やはり、そうですよね。
今後は今と同様に、いろいろ検証するスタイルで行く予定です。
ご意見ありがとうございました。