以前福岡地裁であった判決ですが、右直事故について「直進被害者の赤信号無視」を見逃したまま起訴し、信号無視が発覚した後も起訴取消にしなかったことから炎上した件がありましたよね。

過失運転致傷については、信頼の原則を否定する特別な事情を検察官が立証できず、信頼の原則が適用される事案として無罪に。
この事故は過失運転致傷だけでなく、道路交通法違反(事故報告義務違反、72条1項後段)にも問われましたが、事故報告義務違反も無罪。
その理由はなかなか興味深い。
⑴ 本件事故によって、B車両は転倒しなかったものの、Bは、両車両の間に右足を挟まれ、公訴事実記載のとおりの傷害を負った(甲5。なお、この傷害の事実は、道路交通法72条1項後段所定の報告義務を基礎付ける事実としては、略式起訴の当初から訴因に掲げられていない。)。
また、本件事故により、被告人車両には、左側前方のバンパー部分に2ないし3cm程度の幅の擦過痕が付くなどし、B車両は、右側のブレーキペダルが車体側に押し込まれるようにして曲損するなどした。もっとも、いずれの車両についても、何らかの部品の欠落や落下を伴うような損壊はなかった(甲11)。⑵ 本件事故後、被告人とBはいずれも各自の車両に乗って本件交差点付近の歩道上に移動して停車し、午後7時5分頃に約1分間にわたって路上で話をした。この際、被告人が自車の損傷に気付いて言及する場面はあったが、B車両の損壊については、被告人とBのいずれも言及することはなかった。
この会話の後、Bは、警察への通報をすることなく、自車を運転してその場を立ち去った。残された被告人は、しばらく事故現場近くの施設の駐車場付近にとどまっていたが、午後7時21分頃、警察への通報をすることなく帰途についた(甲7、B及び被告人の各公判供述)。
Bは一旦自宅に帰ったが、妻の運転する車両で事故現場付近に戻り、午後8時10分頃までに110番通報をした上、臨場した警察官に本件事故の発生を報告した(甲1、Bの公判供述)。Bは、本件事故に関し、いかなる刑事処分も受けていない。
※「B」は被害者(直進)。
なぜ事故報告義務違反も無罪なのでしょうか?
4 報告義務違反の構成要件該当性及び可罰的違法性の有無
以上のとおり、本件事故の結果について被告人が認識していたのは、自車に生じた極めて軽微な損傷の事実のみであったことが認められる。このことを前提に、被告人の報告義務違反についての構成要件該当性及び可罰的違法性の有無について検討する。
⑴ 道路交通法72条1項後段が報告義務を課しているのは、個人の生命、身体等の保護、公安の維持等を職責とする警察官に速やかに所定の事項を知らしめ、負傷者の救護及び交通秩序の回復等について車両の運転者等の講じた措置が適切妥当であるか等をその責任において判断させ、もって、職責上取るべき万全の措置を検討、実施させようとするものと解される。したがって、たとえ事故によって生じた結果が軽微であり、道路上の交通にも支障を来していないと思われるような場合であっても、同条項所定の報告義務を免れることはないというべきである。
本件においても、被告人が本件事故の発生を認識していた以上、これによって道路上の交通に特段支障を来しておらず、かつ、被告人が自車の極めて軽微な損傷の事実しか認識していなかったとしても、同条項所定の報告義務を負っていたとみるべきである。弁護人は、被告人が外国人であり、事故後に電話で相談した3人の知人からも通報してもどうしようもないとの助言を受けたことなどから、110番通報を行うのが事実上困難であったことなどの事情を主張するが、それらの事情を踏まえても、被告人が報告義務を免れるものではない。被告人が警察官への報告を怠った点が、形式的に報告義務違反の構成要件に該当することは否定できない。⑵ もっとも、被告人が形式的に報告義務違反の構成要件に該当するとしても、本件においては、報告を受けた警察官に必要な措置をとらせる実質的な要請が相当程度低いといえることに加え、前記第3で検討したとおり、そもそも本件事故の主たる原因は、B車両が赤色信号に従わず本件交差点内に進入したことであり、Bのほぼ一方的な過失によって生じたものである。本件事故の結果についても、被告人が認識していたのは、極めて軽微な自車の損傷の事実のみであり、自らを専ら被害者と認識するのが当然な状況といえる(なお、前記のとおり、検察官は、略式起訴に係る第2事実の公訴事実においては、当初から判明していた被告人車両の損傷の事実を記載していなかった。)。さらに、本件事故後のBは、警察官への通報をすることなく、被告人を残して現場から立ち去っているのである。
このような状況を踏まえると、自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない。第2事実についても、被告人は無罪である。福岡地裁 令和5年10月27日
軽微な事故でも事故報告義務違反を免れないし、被告人の行動は「直ちに報告する義務」に反していたとする。
一方、事故の状況からして警察が臨場して必要な措置をとる必要が薄かったことや、被告人は自らを「赤信号無視のバイクに突っ込まれた被害者」と認識していたこと、被害者Bは警察に通報せず立ち去っていること(形式上Bも報告義務違反が成立するはずが、刑事訴追されていない)を挙げ、刑罰を科すほどの可罰的違法性はないと判断。
この判断は妥当と言えますが、そもそも警察と検察が雑な捜査をして起訴するから話がこじれた印象なのよね。
条文の構成要件に該当したから直ちに有罪とする話ではなくて、非難の対象になるものが有罪なのだから。
被害者Bが道路交通法違反(事故報告義務違反)として有罪になっていたなら話は変わりますが…被告人は軽微な物損事故の「被害者」だと認識していたのだから仕方ない。
ところでこの事件(過失運転致傷)は、昭和40年代に最高裁が示した信頼の原則からすると、「信頼の原則を否定する特別な事情」を示さない限り有罪にはならない。
検察官が起訴取消にしなかった理由は「特別な事情」を示せるという自信があったのか、それともメンツ的な問題なのかはわからない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


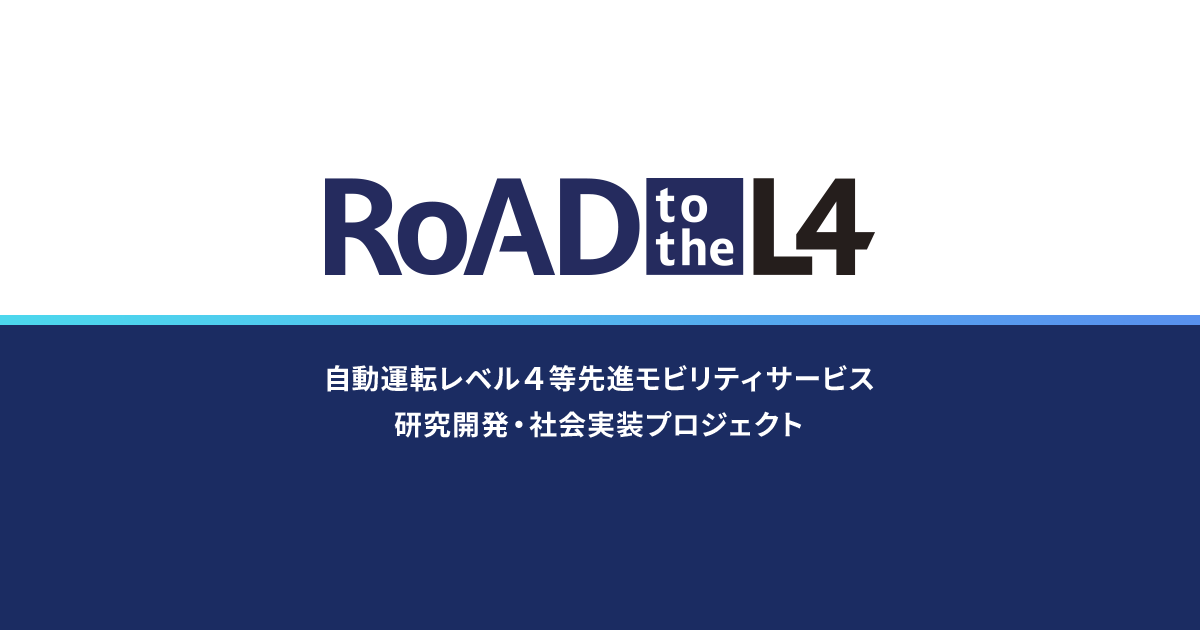


コメント