横断歩道は手を挙げて渡りましょうね!というのは、もはや幼稚園までなのかと思うこともありますw
国家公安委員会が告示として出している、交通の方法に関する教則というものがあります。
これ自体は道交法108条の28に基づく外局規定(告示)なのですが、43年前までは、信号機がない横断歩道では手を挙げて渡りましょうと書いてあったそうです。
ところが理由は不明ながら、手挙げ横断は廃止に・・・
2021年になって、このルールというか努力義務が復活しています。
手挙げ横断

43年前までは、交通の教則(国家公安委員会告示)に、手を挙げて渡りましょうという努力義務があったそうです。
なぜ削除されたのかについては、理由はわからないらしい。
どうも諸説あるようで、
・手を挙げれば車が必ず止まってくれると思い込む危険性
・笑点の挙手が関係している?笑
・タクシーが勘違いする
・四肢欠損等の障害者や、健康上の理由で手が挙がらない人への配慮?
まあ、どれも説得力があるような、無いような論ですw
しかし令和のこの時代になって、教則に復活したというわけです。
これにはいろいろ理由があるようですが、長野県の女子高生が行った研究結果も関わっているっぽい。
横断歩道で歩行者が手を上げれば、車の9割近くは止まってくれる――。女子高校生の研究結果をきっかけに、長野県では秋の全国交通安全運動(21~30日)で、横断歩道でのマナー向上に取り組むことになった。女子高校生は手を上げることで、車の停止率が大きく上がることを調べ、県警にマナーアップ運動を提案した。18日、交通安全運動の出発式で、「歩行者もドライバーも、お互いに思いやりを」と呼びかけた。
(中略)
自ら「歩行者役」となり、自宅近くの横断歩道で、渡る前に手を上げた時と、そうでない時の車の停止する割合を比較した。手を上げない時は35%(102台中36台)だったのに対し、手を上げた時は88%(50台中44台)だった。
長野駅前では通行人に声を掛け、日頃の運転について尋ねた。停止しない理由として「歩行者に気付かないことがある」という回答もあり、手を上げて、ドライバーに横断の意思を伝えることが大事だと考えた。
ほかの都道府県でも同様の試験があった様子。
これらを元に、令和のこの時代になってから手挙げ横断が推奨されることとなったわけです。
個人的に思うことなんですが
私が気になった箇所はこちら。
止まった車に、歩行者も「手を挙げる」「軽くお辞儀する」といったマナーを実践している人が目立ちます。
道交法では、車両側に一時停止義務を課しています。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
なので法律を順守するなら、車が停止するのが当たり前とも言えます。
けど人として、止まってもらったら軽くお辞儀をするというマナーを実践している人が目立つとのこと。
車のドライバーからしても、感謝されて嫌な気持ちになるヒネクレ者以外は、いい気分になれるわけだし。
法律は法律として置いといて、人として当たり前のマナーを実践しましょうということですね。
こういう行動が、ちゃんと止まろうと思う心理にもつながるわけですし。
道路上ではマナー不要とか語りだすような人もいるわけですが、ルールで全てが解決できるわけではないですしね。
まあ、そもそも法律を理解せずに勝手な解釈を使う人もいるので困ったもんだなと思うことも。
ロードバイクでもそうですが、明らかに車から譲ってもらったと思うことってありますよね。
そりゃお辞儀するなどしますよ。
交通の方法に関する教則
国家公安委員会が出した、交通の方法に関する教則は法令なのか?という議論があるのですが、名称が教則となっているからややこしい。
正式名称は昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号。
外局規則・告示に当たります。
告示の法規性については判断が割れることもあるのですが、教育指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)でも法規だと認定されていますからねぇ・・・(平成2年1月18日、最高裁第一小法廷)。
【~しましょう】というのは努力義務。
【~しなければなりません】とある部分は、道交法の規定を具体化しただけなので義務があるとみなせる。
もし教則に【横断歩道では手を挙げなければならない】と書いてあったら、それは道交法に規定が無いので問題になるでしょうけど、あくまでも努力義務・推奨事項として【手を挙げましょう】に留めている。
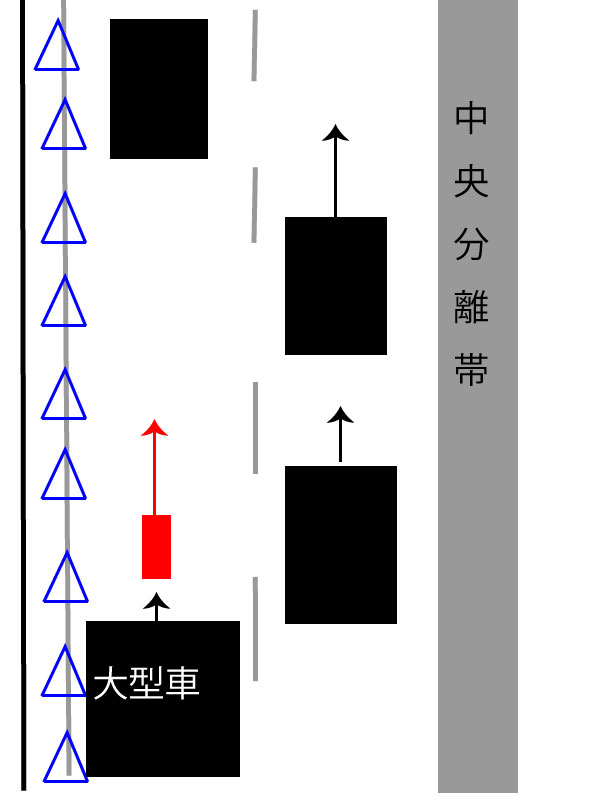
なぜそこまでブロッキング走行をしたがるのか私には理解できませんが。
ていうか皆さん、そんなに追越しされるときに側方距離が近い経験が多いんですかね?
10年乗っていて、数回あるかどうかの経験なので。
まあその代わり、おかしなババアに絡まれたりレアな経験はしてますがw

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


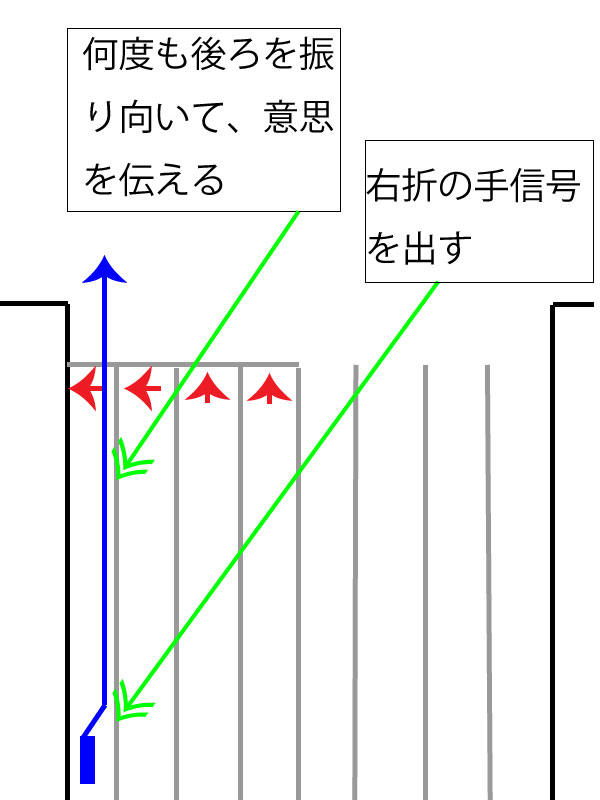

コメント