こういうツイートを見ていると、果たしてそうなのか?という疑問が沸いてきます。
安全のためにはハイヒールで自転車に乗ることが好ましいとも言い難いとは言え、違反だと断定出来るのか?について検証してみます。
■ハイヒールで走行⁰(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールだとペダルの制御ができなくなる可能性があるため、道交法に抵触するケースも。指摘したら足元を切って再投稿。
誰か区長に「常識」をください。#岸本聡子
#杉並区 pic.twitter.com/9alDp7n9Rn— ALICE (@Conductor_ENTJ) July 27, 2023
なお、政治的な話は一切しません。
ハイヒールで自転車に乗ることが道路交通法違反なのか?

まず、根拠として「安全運転義務違反」(道路交通法70条)を挙げていますが、
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
70条安全運転義務については、あくまでも他の具体的義務付け規定ではまかない切れない部分を補完するために存在し、違反の成立についてはシビアです。
ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第70条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。右のような趣旨から、同法第70条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)
昭和43年1月15日 いわき簡裁
なお、70条と他の具体的義務規定は法条競合の関係にあるため、具体的義務付け規定に抵触する場合には安全運転義務違反は成立しません。
道路交通法70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右70条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当である
最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日
ところで。
安全運転義務違反は成立要件が厳しく、「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ」とあるので、いかなる状況であったのかを認定する必要があり、その上でその行為が「他人に危害を及ぼさないような速度か方法」であったかを認定する必要がありますが、例えば出前の岡持ち2輪車について、片手運転がすぐに安全運転義務違反になるわけではないとした2つの判例があります。

森簡裁 昭和42年12月23日判決は、出前の岡持ち2輪車が片手運転した件について無罪(安全運転義務)。
遠軽簡裁 昭和40年11月27日判決では同じく片手運転の2輪車について交差点部分の人や車両の通行が頻繁な場所で片手運転した点を有罪(安全運転義務違反)としながらも、それ以外の場所で片手運転した点は安全運転義務違反が成立しないとしています。
2輪車の片手運転が好ましいことではないにしろ、安全運転義務違反の成立は要件が厳しい。
これら無罪判決を受けて、2輪車の「モノを持った」片手運転については公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)にて規制することにしたものと言われますが、公安委員会遵守事項では「履き物」についての制限があります。
東京都の場合
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
確かに、ゲタや木製サンダルを履いて運転することについては公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)として規制対象になっていますが、軽車両は除外なんですよね。
公安委員会遵守事項では明確に軽車両が除外されてますし、安全運転義務(70条)については
・「その状況下で」ハイヒールで乗ることが他人に危害を及ぼすものと言えるのか?
これらを確定させないと安全運転義務違反にはならないのですが、公安委員会遵守事項の「履き物規定」から軽車両が除外されている趣旨や、あくまでも公安委員会遵守事項(71条6号)が安全運転義務(70条)より優先的に適用されること(法条競合)、具体的状況と危険が特定されてないこと等を考えても、ハイヒールが直ちに安全運転義務違反だと断定するのは論理の飛躍としか言えないかと。
けどネット上の記事では、安全運転義務違反と断言しているものもありますね。
公安委員会遵守事項違反を理解してない点や、安全運転義務違反の判例をみたりしたことがない人が書いたものと思われますが。
安全運転義務違反(70条)の成立要件が厳しいために、各都道府県が安全運転義務違反にはならないものの中から規制したいものを公安委員会遵守事項で具体的に定めているのに、公安委員会遵守事項違反で除外されているのに同じ内容が安全運転義務違反になるというのはだいぶムリがあるとしか。
公安委員会遵守事項で「軽車両を除く」がなければ違反とみて間違いないですが…
交通の方法に関する教則では、「してはいけません」ではなく「しないようにしましょう」としていますが、直ちに違反とは解釈できないのであくまでも非推奨事項扱い。
1 自転車に乗るに当たつての心得
(6) げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましよう。
クルマの運転については「してはいけません」と禁止扱いになっています。
第1節 安全な発進
2 運転姿勢など
(2) 運転するときは、活動しやすいような服装をしましよう。また、げたやハイヒールなどを履いて運転したりしてはいけません。
なお、「ゲタや木製サンダル等」にはハイヒールを含みます。
好ましいとは思いませんが

じゃあハイヒールで自転車に乗ることが好ましいことなのか?というと、個人的にはさほどオススメしがたいというか、転倒しそうになって足をついたときに捻挫しそうな予感。
もちろんそれは単なる「自爆」なので、70条が規制する「他人に危害を及ぼす方法」には該当しないですが。
ハイヒールで乗ることが安全運転義務違反だと断定することはムリだけど、ハイヒールで自転車に乗ることはオススメし難い。
違反の問題なのか、オススメしがたい話なのかは分けて考えたほうがいいと思いますが、安全運転義務違反ってなぜかカジュアルに使いたがる人が多いのも現実。
なんでなのだろう。
なお、片手運転を無罪(安全運転義務)とした判例はこちら。

公安委員会遵守事項の「履き物規制」で軽車両が除外されている趣旨を考えると、「具体的義務を補完する規定」である70条が適用される余地はないのですが、インターネット上の怪しい記事よりも専門書をオススメします。
それは罪の重さからも明らかでして、例えばオートバイをハイヒールで運転したら71条6号(公安委員会遵守事項違反)、自転車をハイヒールで乗ったら70条(安全運転義務違反)だとすると、刑罰がおかしくなるのよ。
| 公安委員会遵守事項違反(71条6号) | 安全運転義務違反(70条) |
| 五万円以下の罰金(120条1項10号) | 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金(119条1項14号) |
仮に自転車ハイヒールが安全運転義務違反になるなら、オートバイが同様の違反をした場合よりも刑罰が重くなりかねないという意味不明な状況すら起きてしまうわけでして。
公安委員会遵守事項違反(履き物規制)で軽車両が除外されている趣旨を考えても、ハイヒールで自転車に乗ったから安全運転義務違反というのはほぼ無理でしょう。
強いていうなら、ハイヒールを履いていたことにより事故を回避できなかったみたいな状況があれば別ですが。
「安全運転のためには好ましくない」と、「安全運転義務違反」は別次元の話。
ハイヒールで自転車に乗ることは前者なので安全運転義務違反だと糾弾するのは的外れ感がありますが、好ましいか好ましくないかでいえば「好ましくない」としか言えないわけですね。
別にこの人を応援するわけでもありませんが、こういう誤解から「ビンディングペダルは安全運転義務違反」などと語る人まで出てくるわけで、ちゃんと専門書や判例から検討してないネット記事は迷惑なんですよ。
けど、公安委員会遵守事項違反から軽車両の履き物が除外されている趣旨などから総合的に判断すると、「安全運転義務違反だとするのは拡大解釈」と思われますが。
ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第70条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。右のような趣旨から、同法第70条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)
昭和43年1月15日 いわき簡裁
民事では過失になりうるとしても、それは事故が起きたからそうなるわけであって、刑罰とは意味が違う。
「オススメしがたい」ならわかるけど。
そんなことよりもヘルメットのかぶり方のほうが気になりますが…まあ、違反にならなくても非推奨事項扱いなのは間違いないので、あまり誉められたモノとも言えませんね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

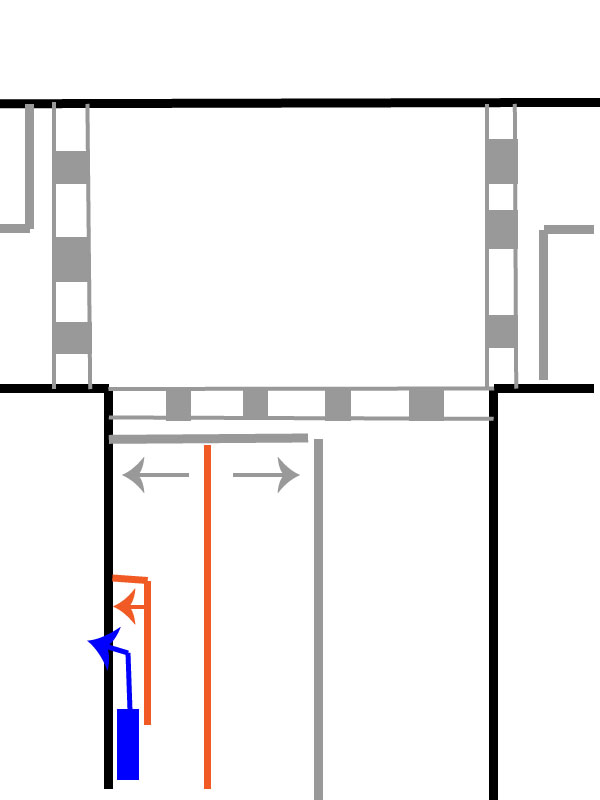
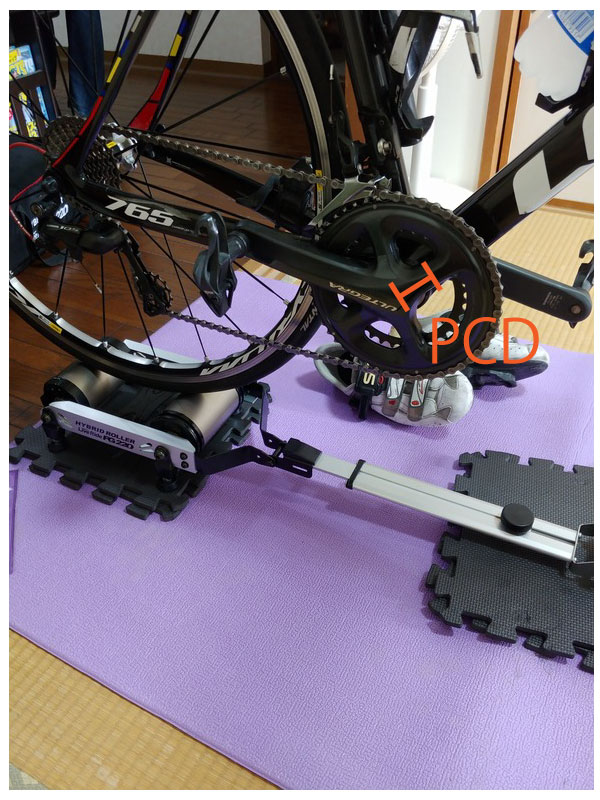
コメント