読者様から、「歩道に対し自転車通行部の表示をする際は 幅員1.5m以上という明確な規定」ってどこにあるのか?と質問を受けたのですが、
歩道に対し自転車通行部の表示をする際は 幅員1.5m以上という明確な規定がある。
これは、自転車が安全に通行する為には1.5m以上の幅が必要だと示唆している言葉で間違いないと思う。
なので、日本の法律では自転車の通行の設計をする際は1.5m以上が基本的な考え方になる。 pic.twitter.com/U6XLza9nO6— 赤カメラ/akacamera (@akacame) November 14, 2024
うーん…歩道の普通自転車通行指定部分(法63条の4第2項)の幅を指定した法律は私が知る限りはないかと。
法律ではなく、警察庁の指示事項(交通規制基準)には原則1.5m以上を確保するようにとしてますが、
8 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分を指定する場合は、次の事項に留意すること。
(1) 通行部分を指定する場合は、歩道の車道寄りを指定することとし、通行部分の幅員は原則として1.5メートル以上を確保すること。また、特例特定小型原動機付自転車、普通自転車及び歩行者のいずれもが安全、かつ、円滑に通行できるようにそれぞれの通行実態に見合った配分とすること。

これを持ち出すのは理論としては危うい。
というのも歩道の「普通自転車通行指定部分」は双方向通行なので、対面通行する自転車を前提にして「原則1.5m以上」。
つまり自転車1台分だと半分の0.75mだろ!という反論を招くので、こんなもんを引用しないほうがいいような。
ちょっと前に恣意的な情報操作を繰り返していたウッディさんとかなら、そういう指摘をするでしょうね。
このような主張に対しては「例外的に歩道通行する場合を想定した双方向前提の1.5mなので、双方向前提ではない車道とは無関係な基準」としか言いようがない。
まだ施行令1条の2でいう「車両通行帯の幅員」を挙げたほうがマシですが、

これにしても例外的に1.0mまで縮小可能としているのが痛い。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
まあ、ワケわからん話をすると墓穴を掘るだけだし、道路交通法18条1項でいう左側端寄りの範囲は道路状況によって違うから数値規定も罰則もないという立法経緯を考えると、「◯◯メートル」にこだわること自体が的外れなのかもしれませんね。
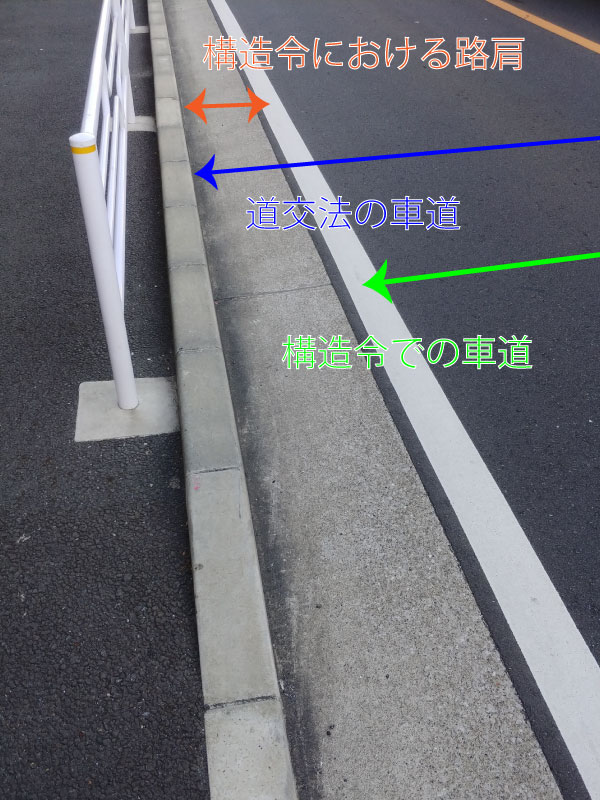
建前上、通行位置を分けただけで実際には重なるものなのだから、追い越し追い抜きは安全確保してやりましょうとしか。

けどこの解釈って根拠がない独自論を語る人が多いので、ややこしい。
そもそも自転車ナビラインの狙いっていくつかありますが、自転車が車道を通行することが当たり前なんだとドライバーに示すもの。
残念ながら「自転車が車道を通行するのは違法!」と勘違いする人すらいるので、そういう人に対し
「あんた、間違いやで」
とアナウンスする効果なんだろうなと思って見てます。
けど歩道の普通自転車通行指定部分の基準なんか持ち出したら話が混乱するだけだし(双方向通行基準1.5mをこの場に出すのは不適切)、法を理解してない人は余計なことを言わないほうがいいんじゃないかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



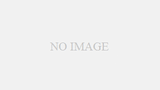
コメント