なかなか興味深い記事が配信されてますが、
ETRTO の新しい規格では、リムの内側の寸法とそれに取り付けられるタイヤのサイズの間に少なくとも 5mm の重複がなければならないと規定されています。これは、以前は一般的だった 25mm 内部リムと 28mm タイヤの組み合わせが、現在は新しいガイダンスの範囲外にあることを意味します。
あくまでもフックレスリムについての話っぽい。
Contents
5mm

ETRTOの新しい基準として、リム内幅とタイヤ幅の関係性では、タイヤ幅が5mmリム内幅よりも広くないとダメという方針にするらしい。
ただし、読んだ限りではフックレスリムの話のようなのと、あくまでも「推奨事項」として検討されているらしい。
つまりリム内幅25mmであれば、推奨タイヤサイズは30mm以上になると。
タイヤが外れるリスクがあるからという理由らしいけど、フックレスリムを採用しているブランドって、基本的には市販されているタイヤとの適合性(外れないか)を独自に検査して、その結果を公表してますよね。
例えばジャイアントのカデックスなど。
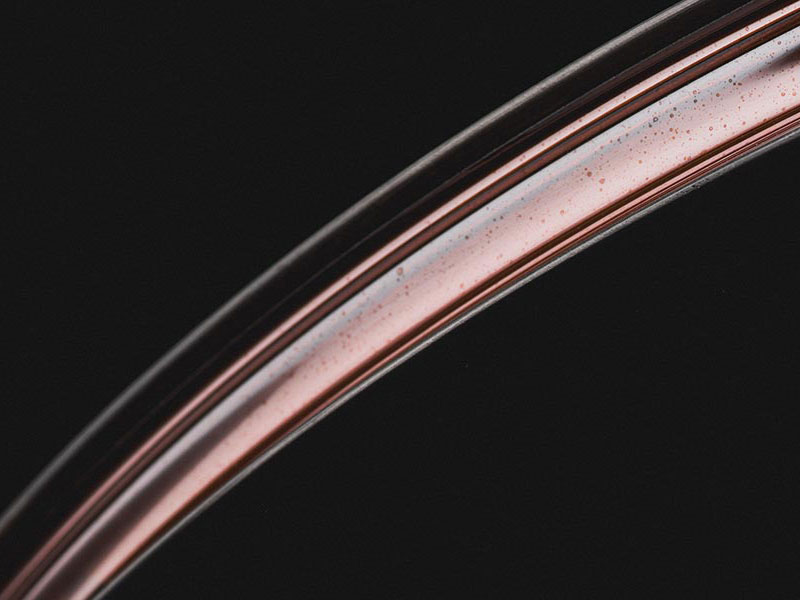
ジャイアントカデックスについては、検査法も公開されてます。
高圧耐性テストと高圧ブレーキテストに合格したタイヤを公表しているのですが、基本的にはどのブランドも似たような検査をしているはず。

「Zipp は、内幅 23 mm および 25 mm の人気があり専門的に証明されたホイールセットをいくつかテスト、設計、開発してきました。過去数年間に 25mm リムに 28c タイヤを装着したホイールセットが十分に使用されており、その組み合わせが安全であり、実証済みのパフォーマンス上の多くの利点が得られることが証明されています。」
実際のところ、どうなのでしょうか?
ユーザーが置いてきぼりに

この手の問題で懸念されるのは、万が一が起きた場合の補償問題なのかもしれません。
少なくともメーカーが発表した互換性通りに正しく使っていたなら、万が一が起きたとしても補償の対象になるでしょう。
ただし今後はETRTOの推奨事項に合わせて、各メーカーが互換表を変えてくる可能性も無くはない。
フックレスリムを使っている人は、ちょっと注意してメーカーの動向を追ったほうがいいかもしれませんが、ほぼ聞いたことがないのよね。
脱輪の話って。
古くは、クリンチャーリムにチューブレスタイヤを使い、パンクして脱輪してタイヤがフォークやフレームに絡まってホイールロックして爆死…みたいな話もありましたが、それはそもそも互換性が全くないのに使ったユーザーが悪い。
けど、互換性がないのに試したくなる漢は昔から絶えませんね。
今まで何ら問題なく使っていた人が、急に「5mmガー!」と言われても困惑するだけな気もしますが、しばらくは要チェックなのかもしれません。
まあ、0.01mmの差で大騒ぎするのが漢だった気もします。
タイヤと同じくゴム製品の話だったかな…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント
リム内幅に対する推奨タイヤ幅ですが、脱輪と聞くとリムからタイヤが外れるという事象を想像する方が多いと思います。
脱輪履脱輪なんですが、実は低圧でビード落ちしやすくなるというのが非推奨の理由です。
クリンチャーの頃から良くある話ですが、細いタイヤで高圧の方がよく転がるという理由で細いタイヤを履く行為がありました。
小径タイヤでよくやる人が多かったのですが、多くの人がビードが上げられないトラブルになったと思います。
これはタイヤ断面の長さが足りず、空気圧を上げてもビードが上がりきるまで広げる事が出来ない短さになっているのが原因。
小径タイヤはリム幅とタイヤ幅の組み合わせが結構狭いので、ビードを上げる時点で上がらない現象が出るんです。
さて700Cになると、ビードは上がりますが、タイヤはトレッド面が扁平して常にビードを落とす方向にテンションが掛り続けます。
これで低圧ですと、チューブレスならちょっとした衝撃でげっぷで空気が抜けビード落ち、最後に脱輪。
クリンチャーでもビード落ち、チューブがパンク、脱輪となります。
問題なのは脱輪では無く、ビード落ちする方向にタイヤが引っ張っている状態な点です。
内幅25Cで28Cタイヤを許可しているホイールですが、ほぼ旧ETRTO規格の28Cのはずです。
こいつは新規格よりタイヤ断面長が長いので5mm以下でも問題無い為です。
新ETRTOでしたら内幅25mmには新ETRTO30cじゃないと推奨外となります。
コメントありがとうございます。
低圧でギャップを踏んだときに、抜けるようになる話はありましたね。
そもそもタイヤの規格にしても新旧どちらなのかは調べないとわからない時代なので、分かりにく過ぎて混乱の原因になっている気がします。