こちらに書いた内容について質問を頂いたのですが、


38条については2項と3項で赤信号の場合を除外しているのに1項については除外してない趣旨を考えると、1項は横断歩道が赤信号の場合でも適用なのではないでしょうか?
これはわりと陥りがちなミスというか、法律の読み方の問題なんです。
Contents
37条の読み方
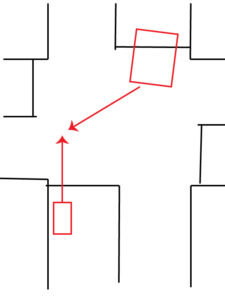
確かに信号については条文上書いてない。
けどこの規定、信号無視する直進/左折車を優先せよという意味はないし、直進車が著しく速度超過した場合も適用がありません。
なぜこうなるか?↓
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
東京高裁 昭和38年11月20日
昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。
富山地裁 昭和47年5月2日
赤信号は「進行禁止」。
進行が禁止されている車両を優先せよというのは意味がわからないので、7条(信号遵守義務)が優先適用される。
優先規定の基本は適法通行車に優先権を与えるものと解釈するのは当然なので、わざわざ条文に書いてなくてもそのように読む。
だからこのような判例が残っている。
38条の2の読み方
次に38条の2。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
これも信号については条文上書いてない。
けど、赤信号無視した不適法横断者には適用がありません。
この規定は昭和42年までは38条1項と2項に分かれてました。
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
横断歩道の規定は当時71条3号。
旧38条1項と2項は横断歩道がない交差点の歩行者優先ですが(横断歩道がない場合とは明記されてませんが笑)、1項は信号がある場合、2項は信号がない場合になっていて、赤信号無視した歩行者は優先権がない(1項)。
なぜ現行規定に改編したかについては、警察庁が説明してます。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課 浅野信二郎)、警察学論集、p37、立花書房、1967年12月
「本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので、今回の改正を機にこの区別を廃止した」とありますが、いちいち条文に書かなくてもそのように解釈するのは当然だから書いてない。
そして現在の38条1項についても同様。
なぜ現在の2項と3項に赤信号除外が書いてあるかというと、1項は歩行者優先規定なのに対し、2項は直接的には優先規定ではなく、優先規定を補強する意味でしかないから。
優先規定であればわざわざ「赤信号除外」と書かなくてもそのように解釈するのは当然ですが、2項と3項は優先規定じゃないから「赤信号除外」と明示しないとダメなのよね。
これら判例や警察庁の解釈からみても、37条、38条1項、38条の2は「信号無視した歩行者や車両を優先する規定ではない」のは明らかかと。
(1)自動車を運転する者は、自車が信号機により交通整理の行われている交差点を対面信号機の青色表示に従い直進する場合でも、自動車運転者として通常要求される程度に、前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるものと解すべきであり、このことは本件の被告人においても同様である。
(2)これに対し、検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項の適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。
検察官は、この主張をするに際し、札幌高裁昭和50年2月13日判決判例タイムズ325号304頁を引用するが、同裁判例は、当該事案における道路および交通の状況等から、前方の横断歩道上に横断中の歩行者がなお残存する蓋然性が高く、運転者においても対面信号機が青色表示に変わった直後に発進したため前方の横断歩道上に横断中の歩行者等が残存している可能性があることを十分予測できた事案に関するものであって、本件とは事案を異にする。
以上により、被告人又は被告人車両には道路交通法38条1項は適用されず、したがって、その適用を前提として高度な注意義務が課されるかのように述べる検察官の主張は採用できない。
徳島地裁 令和2年1月22日
なお、38条の2については直前横断の場合も適用がないとした判例(東京高裁 平成27年8月6日)があります。

結構ビックリするのは、「優先がないなら轢いてもいいというのか!」と発狂する人もいること。
優先がないことは、事故回避義務まで免除するわけがないでしょ…
優先規定と事故回避義務は別問題です。
回避可能な事故は防ぐ義務があるのは当たり前。
追いつかれた車両の義務なんかも速度超過車については除外と考えられますが、条文に書いてないのにそう解釈するのは妥当かと。
ところで旧38条1/2項は「交差点に横断歩道がない場合」とは明記されてませんが、横断歩道がある場合は71条3号、横断歩道がない場合は38条と解釈されてました。
分かりにくいので昭和42年にきちんと直してますが、裁判所の判断はこうなる。
事案は交差点を右折する際に横断歩行者がいたのに一時停止しなかった道路交通法違反ですが、弁護人の主張は「交差点においては71条3号ではなく38条1項が適用されるべき」で、「71条3号は一時停止義務を定めているが38条1項は一時停止義務がない」。
所論は、原判決は 被告人は福岡県直方市津田町交差点において普通貨物自動車を運転通行するに際し歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断しようとしているのにその直前で一時停止をしなかつたものであるとして、道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2を適用している。しかしながら、当時被告人は交通整理の行われていた右交差点を右折していたものであるから、同法第38条第1項に当るかどうかが問題である。けだし、同法第71条第3号は横断歩道における横断歩行者の保護という面では同法第38条第1項とその目的を一にしているが、同法第38条第1項は、特に車両が交差点で左折または右折する際の横断歩行者との関係を規定したもので、同法第71条第3号の特別規定であつて、交差点における車両と横断歩行者との関係については同法第38条第1項が適用されるべきものである。そして、被告人は当時横断歩行者の通行を妨げたことはなかつたものである。したがつて、原判決には法令適用の誤りがある、というのである。
裁判所の判断はこちら。
そこで、検討するに、道路交通法第71条第3号は横断歩道(同法第2条第4号参照。)の横断歩行者と車両との関係を規定したものであるから、交差点またはその附近に横断歩道があるときはその横断歩道の横断歩行者と左折または右折する車両との関係も同条号によつて規制されるものであり、同法第38条第1項は交差点またはその附近に横断歩道がない場合について道路の横断歩行者と左折または右折する車両との関係を規定したものである。したがつて、右両規定は所論のような関係にはない。そして、原判決挙示の証拠によれば、当時歩行者が横断しようとしていたのは横断歩道であり、被告人運転の自動車はその横断歩道の直前で一時停止しなかつたものであることが明らかであるから、被告人は道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2違反の罪の責任を免れない。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。
福岡高裁 昭和42年10月11日
条文上、旧38条1項には「横断歩道がない交差点の場合」とは書いてないけど、こういう判断になる。
要は71条3号との対比で読むわけで、旧38条1項だけを読んでも意味がないわけ。
わりと多い
例えば昭和46年改正以前の徐行義務は、信号がある場合しか明文上の除外規定はありませんが、
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。
最高裁は、明文にない「優先道路と広路車」についても左右の見通しがきかない交差点で徐行義務がないとした(この判断は46年改正で無効化)。
車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難い
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
しかしながら、職権によって調査すると、原判決が、本件交差点を「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に該当するとした判断は、これを是認することができるが、右のような交差点においては、いかなる場合にも道路交通法42条により当然に徐行すべきであるとした判断は、これをただちに是認し難いものと考える。すなわち、右のような交差点であっても、その車両の進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号)にまで減速する義務があるとは解し難い(昭和42年(あ)第211号同43年7月16日第三小法廷判決参照)。
これを本件についてみると、原判決の認定するところによれば、被告人の進行していた道路は、幅員約7メートルの歩車道の区別のない舗装道路であり、これと交差する道路は、幅員6.4ないし5.8メートルの同じく歩車道の区別のない舗装道路であったというのである。また、第一審証人の尋問の際、提出され、本件記録に編綴されている被告人作成の見取図で、同証人も現場の状況と大体一致する旨供述しているもの(2通)によれば、被告人の進路と交差する左方(西側)の道路は先方で幅員が約4メートルになっている事実もうかがわれるのである。そして、これらの状況からみて、本件交差点は、被告人の進路のほうが明らかに広いと認められることになり、同法42条の徐行義務が免除される場合にあたる可能性が全く存しないわけではない。
しかるに、この関係の事実を確定することなく、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないものにおいては、いかなる場合にも当然に徐行義務があるとし、第一審判決を維持した原判決には、法令の解釈適用をあやまった結果審理を尽くさなかった違法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日
なぜ明文にない除外規定を認めたかというと、当時の36条は42条より優先適用されて42条の除外規定と捉える余地があり、それを最高裁が認めたから。
「条文に書いてない!」というのは、法律の読み方の問題です。
そういう理由で「条文に書いてない!」と言われても読み方が違うとしか言いようがないのですが、条文を読んでも理解できるような法律にはなってないので、疑問があるときは立法時の解説を探したり、判例や解説書をみたほうがいいと思いますよ。
そもそもこれ。

47条3項と17条2項で堂々巡り…と解釈しうる余地は全くありませんが、気になって調べた限り47条3項の「停車」とは1項の停車のことであってました。
要は読み方の問題なので…3項は1項2項の特別規定/例外規定なんだと読まないと永久にわからないまま。
そして昭和42年改正以前の旧38条と71条3号の関係性のように、47条3項と17条2項を読めばそれぞれが独立して別の目的で規定していることは読み取れるわけで、「堂々巡り」とは全く読み取れない。
条文をそのまま読んで理解できるなら、解説書は要らないのよね。
条文上書いてない除外が認められた判例をいくつか挙げましたが、条文上書いてないというよりも読み方の問題なのかも。
わりとこのように明文化されてないけど除外があるのは多い気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
札幌高裁昭和49年判決は信号無視した横断歩道でも38条1項の義務があるとしてます。
コメントありがとうございます。
昭和50年2月13日判決の話でしょうか?
その判例は赤信号無視した歩行者ではなく、青信号で適法に横断した残存歩行者の事例です。
赤信号無視した場合と判断が違うのは当たり前。