飲酒運転は違反です。
道路交通法では、呼気検査の数値に関係なく酒気帯び運転を禁止していますが
第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気帯び運転として罰則や行政処分の対象になるには呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上であることが必要。
呼気アルコール濃度が0.16mg/lなのに、酒気帯び運転が成立しないとした判例があるのですが、ある意味興味深い事例です。
東京地裁 令和2年7月3日

この事件は行政訴訟で、原告の訴えは「酒気帯び運転として免許取消処分と一年間免許を再取得できない期間を指定した処分をいずれも取消しろ」。
取消を求める理由は、酒気帯び運転が成立しないからとしている。
まず、事実の整理から。
| 時間 | 出来事 |
| 16:30頃 | C店において,500mlペットボトルに25度の焼酎と水を約1:2の割合で入れた焼酎を飲み始め,そこから(住所省略)付近道路までの約1.6kmを普通自動二輪車で走行する間に,同ペットボトルの約3分の2の焼酎を飲んだ |
| 16:35頃 | 警察官から停止要求 |
| 17:02~17:06 | 水でうがいをした後,風船に呼気を吹き込み,北川式呼気中アルコール測定器DPA-11型に同風船を取り付けて呼気中のアルコール濃度を測定したところ,同日午後5時06分,呼気1lにつき0.16mgのアルコールが検出された |
東京都公安委員会は原告に対し「酒気帯び運転(0.25未満)」を行ったものとして13点を付加。
免許取消と一年間免許を再取得できない期間と定めましたが、原告の主張は呼気アルコール濃度が0.16mgだったことには争わないが酒気帯び運転が成立しないからいずれの処分も取消しろとしている。
さて、酒気帯び運転の基準0.15mg/lを超えながらも酒気帯び運転が成立しないと主張する根拠はなんでしょうか?
原告の主張はこちら。
(1) 平成28年11月3日午後5時06分に呼気1lにつき0.16mgのアルコールが検出されたことは争わないが,呼気検査の時刻は,本来であれば運転を終え自宅で休んでいたはずの時刻であり,同日午後4時35分の運転中のアルコールの程度は立証されていない。運転時点では,呼気中アルコール濃度はそこまで高くなかった可能性がある。
(2) 「酒気帯び運転(0.25未満)」の成立要件である「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは,運転時に身体に保有されるアルコールが呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上が検出される状態であることをいう(以下「A説」という。)と解される。
一瞬何を言っているか分かりにくいけど、原告にアルコール濃度検査をしたのは午後5時06分。
運転していたことを現認され停止したのは午後4時35分。
つまりアルコール濃度検査は「運転後30分経過した時間における数値」で、運転中のアルコール濃度は特定されていないと主張。
被告(東京都公安委員会)の主張はこちら。
(2) 呼気検査結果は飲酒開始から約35分後のものであり,運転中の呼気中アルコール濃度を示したものではないが,本件における原告の飲酒内容と同種の飲酒をした場合,飲酒開始5分後において呼気1lにつき0.15mg以上かつ飲酒開始約35分後よりも多量のアルコールが検知されること,さらに,原告の飲酒内容に基づいてその信用性が確立されているウィドマーク式算定法によって運転時の呼気中アルコール濃度を算出すると0.152~0.255mg/lとなることからすれば,原告が自動二輪車を運転してい
た午後4時35分頃,身体に呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態であったことは優に認められる。
(3) 「酒気帯び運転(0.25未満)」の成立要件である「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは,運転時に体内に呼気1lにつき0.15mg以上に相当する量のアルコールを保有する状態であることをいう(以下「B説」という。)と解される。
両者の主張をまとめるとこう。
| 原告の主張(A説) | 東京都公安委員会の主張(B説) |
| 運転時に身体に保有されるアルコールが呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上が検出される状態である | 運転時に体内に呼気1lにつき0.15mg以上に相当する量のアルコールを保有する状態であることをいう |
なんでこんなことに争いが起きるかというと、
一般に,飲酒後間もない時点までは,血中アルコール濃度は速やかに上昇し,最高濃度に達した後,上昇時に比して緩やかに下降し,このときの下降率はほぼ一定し,血中アルコールの消失曲線はほぼ直線となり,呼気中アルコール濃度もそれとほぼ比例することから,飲酒量から,一定時間経過したときの血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度をウィドマーク式算定法と呼ばれる計算式を用いて求められる

原告の主張は、運転から30分経過した時間における数値は「アルコール濃度上昇期」だった可能性があり、「運転中」のアルコール濃度はそれより低い可能性があったから酒気帯び運転が成立しないと主張。
だから施行令の解釈が「検出される状態」(A説)なのか、「体内に保有する状態」(B説)なのか揉めている。
東京地裁は原告の主張を肯定。
1 前記「2 関係法令の定め」のとおり,施行令別表第2の1の表にいう「酒気帯び運転(0 .2 5未満)」とは,身体に施行令44条の3に定める程度以
上のアルコールを保有する状態(身体に血液1mlにつき0.5mg以上又は呼気1lにつき0 .2 5mg以上のアルコールを保有する状態を除く。)で車両等を運転することをいい,施行令44条の3は,道交法117の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度として,血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mgと定める。
ここで,「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」の解釈につき,原告は,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上(以下,血中アルコール濃度についての言及は省略する。)のアルコールが検出される状態である(A説)と主張するのに対し,被告は,運転時に体内にそれだけの量のアルコールを保有する状態であればよい(B説)と主張する。A説によっても,運転時に呼気検査を行うことは現実的でないから,運転後の呼気検査の結果から運転時における呼気中アルコール濃度を推認することとなるが,A説は,それにより推認される運転時の呼気中アルコール濃度が呼気1lにつき0.15mg以上でなければ「酒気帯び運転(0 .2 5未満)」は成立しないとするのに対し,B説は,運転後の呼気検査により呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出されれば,運転後に追加して飲酒していない限り,運転時には,検査結果に対応するだけのアルコール量又はそれ以上のアルコール量が(消化器官に吸収され血液や呼気に反映される前であっても)体内に保有されていたのであるから,「酒気帯び運転(0 .2 5未満)」が成立するとするものである。
しかし,施行令44条の3は,直接には道交法117条の2の2第3号の委任を受けて,犯罪構成要件の一部である運転時の身体におけるアルコールの保有状態として,呼気1lにつき0.15mg(以上)と定めているのであるから,運転時において呼気中アルコール濃度が上記の程度に達していることが酒気帯び運転罪の犯罪構成要件であり,また,道交法103条1項の委任を受けた政令で定める処分基準の内容となっているのであって,運転時に呼気中アルコール濃度が施行令44条の3で定める程度に達したとは認められないのに,運転後の呼気検査結果が上記の程度を超え,運転時において呼気又は血液以外の器官において同程度のアルコールを身体に保有していたことになるというだけで「酒気帯び運転(0 .2 5未満)」が成立すると解釈する(B説)ことは,法令の文言を離れた不当な拡張解釈というべきであり,酒気帯び運転罪を構成し,処分基準にいう「酒気帯び運転(0 .2 5未満)」を構成する「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0 .1 5mg以上のアルコールが検出される状態であることをいう(A説)と解するのが相当である。(中略)
本件において,原告の飲酒開始時刻は平成28年11月3日午後4時30分頃であることに争いがなく,本件全証拠によっても,当日,それ以前に原告がアルコールを身体に摂取したという証拠はない。
そうすると,その約32~36分後である同日午後5時02分から午後5時06分の間に呼気を風船に吹き込んだ時点では,原告の呼気中アルコール濃度は上昇期にあった可能性があり,運転時である同日午後4時35分頃の呼気中アルコール濃度は,呼気検査時よりも低かった可能性を否定できない。東京地裁 令和2年7月3日
うわー…という判決ですが、もちろん東京都公安委員会は控訴。
東京高裁 令和3年6月17日
東京高裁は以下の理由から原判決を取り消しし、原告の請求を棄却。
1 道路交通法(以下「法」という。)65条1項は,「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めている。この条項は,昭和45年第63回国会において上記のように改正されたものであるところ,同改正前の法65条は,「何人も,酒気を帯びて(身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあることをいう。以下同じ。)」車両等を運転してはならないと定めていた。この改正前の法65条は,「酒気を帯びて」という用語の定義として「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態であることをいう。」と規定しており,政令で定める程度以上に「身体にアルコールを保有する状態で車両等を運転してはならない。」旨定めるものであった。
そして,この昭和45年の改正によって,「政令で定める一定程度」以上に「身体にアルコールを保有する状態で車両等を運転」することを禁じる規定を改め,アルコールの程度のいかんを問わず,およそ「身体にアルコールを保有する状態で運転すること。」を全て禁止することに変更された。
このような改正が行われた趣旨について,昭和45年第63回国会の参議院地方行政委員会において政府委員A警察庁長官は,「非常に急激なモータリゼーションの結果,それに伴いまして事故が非常にふえております。…この道交法について,私どもとしては根本的な実は改正をしたい,こういう考え方を持っております。…そこでとりあえず本年度の改正は,…悪質違反,たとえば酒気帯び運転の禁止…といった当面の改正だけを今年はやらせていただきたい。」「第65条第1項の改正規定は,現行の酒気帯び運転の禁止が,身体に一定程度以上のアルコールを保有する状態で運転することの禁止となっておりますのを,アルコールの程度のいかんにかかわらず酒気を帯びた状態で運転することの禁止に改めようとするものであります。なお,新たに禁止される部分につきましては,罰則を付さないこととしておりますが,これによって,飲酒運転の習慣をなくしようとするものであります。」と答弁している(いずれも乙25・第63回国会参議院地方行政委員会会議録第10号)。
すなわち,この酒気帯び運転に関する昭和45年の法改正は,アルコールの程度のいかんを問わず,およそ「身体にアルコールを保有する状態で運転すること。」を全て禁止することにより,飲酒をして運転する習慣を排除し,飲酒運転による事故の発生を抑止するための根本的な改正であると認められる。2 しかし,昭和45年第63回国会の参議院地方行政委員会における政府委員警察庁B交通局長答弁にあるように,「午前中にコップ一ぱいのビールを飲んで,午後何時かころになってそれが酒気帯びであるのかどうかという境目の判定が非常にむずかしい。…何らの基準なしに,酒気帯びであるからおまえは罰金だという言い方は,どうも法律上は非常に困難であるということで,何らかの限度を設けなければいけない…」(乙26・第63回国会参議院地方行政委
員会会議録第11号)ということで,法119条1項7号の2で「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転した場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」に3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされた。
そして,上記の「政令で定める程度」として,道路交通法施行令44条の3は,「法119条第1項第7号の2の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラムとする。」と定めた。この道路交通法施行令44条の3の定める内容につき,政府委員警察庁B交通局長は,昭和45年第63回国会の参議院地方行政委員会において,「現場で容易に判定し得る限度であり,かつまたいろいろな科学的な検査をやってみますと,少なくとも7割くらいの人がいろいろな機能の障害を,本人は自覚しませんでも機能の障害を来たす程度」であると答弁した(乙26・第63回国会参議院地方行政委員会会議録第11号)。3 このような酒気帯び運転に関する昭和45年の道路交通法の改正の経緯を見ると,改正前の法65条に「酒気を帯びて」の定義規定を置いていたときから,「身体にアルコールを保有する状態」を基準として,法規範が制定され改正されたことが認められる。
そして,処罰対象を明確にするために設けられた,同改正後の法119条1項7号の2(現在の道路交通法117条の2の2第3号)においても,「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」と定め,「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものを罰則の対象とすることにし,「身体にアルコールを保有する状態」の程度によって,処罰対象の基準とすることを決めることとしているところ,これは,前述のとおり,昭和45年の道路交通法改正前からの同法が定める酒気帯び運転に関する一貫した考え方に基づくものである。
そして,昭和45年の道路交通法改正に伴い,上記の「政令」である当時の道路交通法施行令44条の3において,「血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム」という基準が設けられたが,これは,前述の政府委員の答弁にあるように,処罰規定を設ける以上は,一定の基準ないし限度が必要であるところ,現場で容易に判定し得る基準であることや,科学的検査により一定の人に機能の障害が生じることなどを勘案して設けられた基準であって,この政令の基準は,体内にどの程度のアルコールが保有されているかを運転中に測定することがほぼ不可能であることを踏まえ,血液や呼気にそのような変化を生じさせる程度の「身体にアルコールを保有する状態」であることを処罰の基準とするものと解すべきである。4 このような法65条1項の定める酒気帯び運転等の禁止に関する規定や改正の経緯等を見てくると,現行の道路交通法施行令44条の3の定める「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」という基準は,「身体に保有するアルコール」の量の徴表としての数値であると解すべきである。そして,このことは,酒気帯び運転についての違反点数を定める施行令別表第2の備考二の9,5,2の解釈においても,特にこれと異なる解釈をすべき理由は見出し難い。むしろ,このような解釈は,施行令別表第2の備考二の5が「身体に…程度以上のアルコールを保有する状態」で運転している場合と定めている文言とも符合する。
証拠(乙32,35の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,一般に,経口摂取されたアルコールの約95から98パーセントは,胃,小腸等の消化管から吸収され,血流に乗って心臓や脳,筋肉や脂肪組織など全身に保有され,最終的には門脈を通じて肝臓に送られて分解,代謝され,呼気,汗,尿,便などで未変化体のまま直接体外に排出されるアルコールは,摂取量の2ないし5パーセント以内程度であることが認められ,経口摂取された「身体に保有するアルコール」の量は,追加してアルコールを摂取しなければ,減ることはあっても増えることはないところ,本件の被控訴人は運転終了後,呼気検査までの間にアルコールを追加摂取しておらず,飲酒開始後約35分後に呼気検査をした結果,呼気1リットルにつき0.16ミリグラムのアルコールが検出されているのであるから,被控訴人は,道路交通法施行令44条の3の定める基準を超える呼気1リットルにつき0.16ミリグラムに対応する「アルコールを身体に保有した状態」で車両等を運転していたと認められる。そうすると,本件において,被控訴人は,施行令別表第2の1の表にいう「酒気帯び運転(0.25未満)」を行ったと認めることができ,点数13点を付加し,これを前提に東京都公安委員会が,本件取消処分をしたことは適法である。
東京高裁 令和3年6月17日
東京高裁は一審でいうB説を採用してますが、その判断理由として昭和45年改正道路交通法における酒気帯び運転の改正経緯を用いている。
昭和45年改正の経緯は当時の警察学論集などにもありますが、法解釈する上では改正経緯や改正前条文も大事なのよね。
屁理屈なのか、正論なのか?
原告の主張が屁理屈なのか、正論なのかについてはあえて書きませんが、一応法定禁止はあくまでも酒気帯び運転全般を禁止していて、刑罰上の基準が別という構成。
このように堂々と酒を飲み2輪車を運転する人がいるのが現実なので、アルコールインターロックでアルコール検知器とエンジンを同期させたほうがいいのよ。
アルコール検知器に引っ掛かりエンジンが掛からないことが気にくわないなら、機械相手に発狂してもらうほうがマシ。
このような事案を争う人がいるから裁判所が判断するという点では、争うことで明確になるメリットはありますが…
ところで、法律解釈判断をする上ではこのように立法趣旨や改正経緯に立ち戻り検討することは珍しくない。
文理解釈も大事ですが、困ったときは新設・改正経緯や理由を確認することが大事。
行政訴訟なので処分の適法性は行政庁に立証責任がありますが、行政訴訟が行政有利と言われるのは、様々な資料や証拠を集める能力が一般人と差があることが大きい。
38条2項の解釈にしても、行政側は様々な資料をたくさんの職員を動員して探せるはずですが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

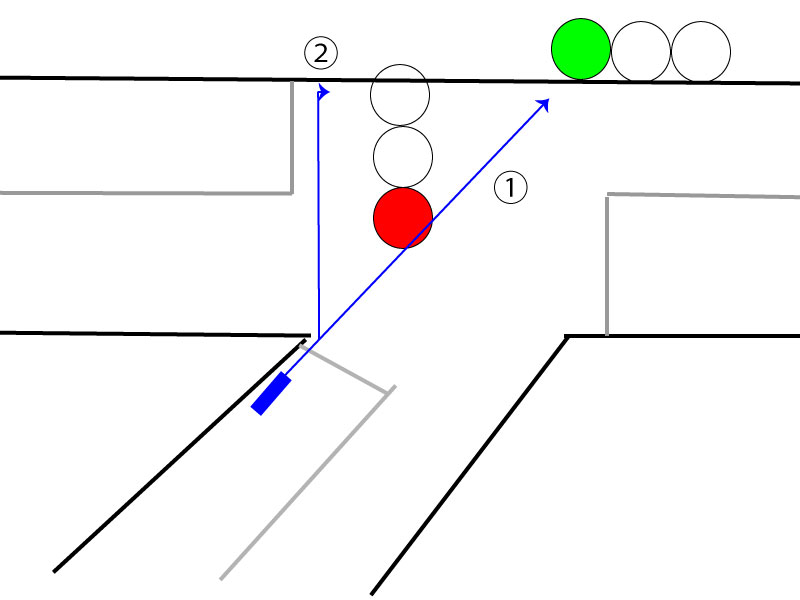

コメント
都市伝説のように言われている、
「飲酒関門に引っかかった時は、とりあえず、ドアをロックして、警察官の見ている前で、酒を飲め。そしたら、運転時の酒気帯びは証明できないから大丈夫」と、
根っこは同じ主張のような気がします。テクニカルにひねりを加えてますが。
しかし、C店から止められるまでの5分間に、水割りとはいえ焼酎を340mlをバイクに乗りながら飲む、とは・・・。一昔前は、喫煙しながらバイクに乗る人もよく見ましたが、そんな感じでペットボトルの焼酎を飲んでたんでしょうね。
その上、止められてからは、30分もゴネてたとは、ちょっと呆れます。
コメントありがとうございます。
そして東京地裁ときたら…