先日書いた記事の内容。

シートクランプがクイック式だとトルク管理不可能なので、まあ、論外ですよね。
それと同時にトルクレンチって持っていたほうがいいの??という話になるのですが、

けど過信は禁物と、使い方間違っていたら意味がない。
Contents
トルクレンチの基本

例えば私のバイク。
シートクランプのところ、4N.mと書いてありますが、4N.mで締めればいいわけではありません。
この数字は最大トルクなので、4N.m以下で固定しろという意味。
一般的には、4N.mと書いてあったとしても、それを超えた瞬間にバキっと壊れるわけではないです。
多少安全マージンを持たせて数字を書いているはず。
なのでこういう場合、まずは3N.mをちょっと超えた数字あたりをトルクレンチで指定して締めてみる。
そしてサドルに体重を掛けて動かなければそれでOK。
次に使い方。

このトルクレンチは、クリクリ回すことでトルク値を指定できます。

なので締めるトルク値を決めるのがまず最初。
次に、ハンドルを持つ位置ですよ。

ここが正しい持つ位置。

こっちはダメな例。


力点と回転軸の距離が変わってしまうので、メーカーが想定していない位置をもってトルクレンチを使うと、指定した数字通りになりません。
あとこのトルクレンチは、指定トルクになるとカチッと動きます。
カチっと動いたところからもう一回カチッとさせると(ダブルクリック)、オーバートルクになってしまいます。
・ハンドルを持つ位置を正しく
・ダブルクリック禁止
トルクレンチの狂い

私が使っているバイクハンドのトルクレンチは、校正不可能になっています。
ただしこれ、いつかは狂っていくもの。
なので100%信用できるモノとも言えません。
狂ったトルクレンチでやっても、意味がないのは誰しも理解できるところ。
高いトルクレンチだと、メーカーに出して校正してもらえるそうですが、
ショップだと、毎年校正して使っている・・・と信じたい。
一般人レベルだと、いかに狂わないようにするかが大切です。
まず、保管時には緩めておくこと。

私が使っているバイクハンドのものは、保管時に2N.m以下にするなという指定が付いています。
なので2N.mにして保管。
次に、錆などがあれば狂うので、湿気などに気をつけること。
雑な保管をしていると、知らぬ間に狂ってしまう可能性もあるわけです。
さらに、締める方向のみに使い、緩める作業には使わないこと。
緩める動作で使うと、結構な狂いが出るという話もあります。
最後に、衝撃と振動で狂う可能性があるので、下手に地面に落としたり、振動が加わる場所で保管しないこと。
こういうのもどれだけ狂うかは未知数なので、校正できるタイプなら年に一回くらいは校正したほうがいいんでしょうね。
・湿気大敵
・緩める方向には使わない
・衝撃や振動に注意
正しく使うこと

もしもの話ですよ。
テキトーな保管状況で、緩める操作にも使いまくって、ハンドルを持つ位置もテキトー。
そんな状況でトルクレンチを信用して使えば、全然違うトルクが掛かっている可能性も否定できないわけです。
なので100%信用できるものではない。
で、職人さんの中には手ルクの人もいます。
私がよく行くショップも、たぶんトルクレンチ使ってないんじゃないかと思うのですが(詳しくはわかりませんw)、結構緩めで固定されていたりします。
緩めと言っても、パーツが動かない範囲で最大限緩くみたいな。
そのため、定期的に増し締めチェックしないとダメなんですが、本来、パーツが動かない範囲で最大限緩くが原則。
それ以上は過剰トルクになっている可能性もありますし。
けど職人と同じ感覚を身に着けることは無理なんで、一般人はトルクレンチを、なるべく狂わないように保管し正しく使うしかないわけです。
私が使っているのは台湾メーカーのものですが、あんまり安すぎるトルクレンチも不安・・・かな。
トルクレンチでカーボンパーツを破壊した話も聞いたことがあるのですが、使い方が悪かったのか、指定トルクが悪かったのか、トルクレンチの管理が悪かったのか、トルクレンチの精度がイマイチだったのか、原因はわかりません。
まあ不安だったら、ショップ任せにしてしまうのもアリ。
自分が破壊したなら自己責任だけど、ショップが破壊したらショップの責任だから・・・なんて書いたら怒られそうですが、ショップレベルでも慣れていない店員が破壊したなんて話もあったりするので、意外とややこしいんですよ。
まあ、信頼できるメカニックを見つけて、その人にだけお願いするというのがベストなのかもしれません。
チェーン店だと下手するとバイトが作業するとか聞きますが、どうなんでしょうかね。
ちなみにですが、こういう繊細さを嫌って、カーボンパーツを使わないという選択肢もあります。
アルミだろうとクロモリだろうと、オーバートルクになるのはよろしくないですが、カーボンよりは許容範囲が広いことは確か。
クロモリだから雑でもOKではないですが、カーボンよりはトルク管理に気を遣わないことは確かですし。
前にも書いたように、コーダーブルームがマスターレーサーというクロモリフレームを出してますが、

クロモリ界では評価が高いマツダ自転車工場のフレームがこの値段なので、お買い得ではあると思います。
まあ、カラーオーダーなどを一切排除しているからこの値段なんでしょうけど、個人的には結構興味あるw
BIKE HAND(バイクハンド) YC-617-2Sコンパクトトルクレンチ ブラック
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



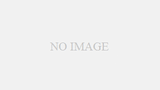
コメント
トルクレンチはそこそこ名の知れたメーカーでも最初から狂ってることは稀にあります。校正証明書が付属しているようなものですら。構造上仕方がない部分もあるので避けられません。安物は不明ですがプレート型が新品で狂ってることはまずないみたいですのでプリセット型の場合の話です。測定機器全般で安物は微妙です。工業製品でコストが掛かるのは調整と検査なので、真っ先に削られる工程。私の場合はトルクチェッカーを持っている店で買って、その場で狂ってないか確認して貰います。決まったトルクで締め付けるならプリセット型ですが、カーボンパーツのようにトルクを探るような使い方をするなら、リアルタイムでトルクが表示されているプレート型の方が使いやすいです。作業スペースが取れればですが。
コメントありがとうございます。
検査工程が真っ先に削られるというのは、中華カーボンフレームに走行テストなどをしないことでコストダウンしているのと似てますね。
プレート型とプリセット型で差が出るのは知りませんでした。
検査工程が減らされるのは工業製品あるあるですね。形は同じなのに材質が変えられたり、生材に置き換えられたりで耐久性が別物もあります。電気関係だと安全回路が削られます…
プレート型はしなりを利用していて可動部分が全く無いのと、プリセット型と違い保管時にテンションが掛かっていないので非常に狂いにくいです。そのため精度の比較用に買う人もいますね。
コメントありがとうございます。
なるほど、プレート型はテンションが掛かってないなら狂う要素はほとんどないですね。
モノ自体が歪んだら別でしょうけど・・・
買った時の箱に入れておけば歪みは問題ないと思います。使用トルクを考えれば上に物を置くとかでもしない限り自重でビームが歪むことは無さそうですが、プレート(目盛板)とか針を引っ掻けて歪ませる可能性の方が高いので注意は必要です。あと基本的にプレート型は締め緩め両方に対応するので、緩ませる時のトルクで元の締め付けトルクの目星をつけたり、逆ネジでも使えたり意外と便利です。
コメントありがとうございます。
私が持っているプリセット型も、一応は逆ネジでも対応する変換レバーが付いてます。
私も詳しくは無いですが、逆方向は使っていると狂いやすいとか聞きますが・・・どうなんでしょうかね?
レバーというのはヘッドのレバーでしょうか?あれはビットやソケットが食いついた時に一時的に逆の力を加えたりするとき用です。
プリセット型の首折れの機構のほとんどは左右非対称なため片側のみ使えます。一部、内部構造が左右対称になっているものや、ビットを取り付ける部分が両面にあって引っくり返すことで両回しに対応したものもあります。あと逆回しで狂うかどうかはメーカー毎に構造が違うため一概には言えませんが、トルクが計れるわけでもないですし、壊すリスクを考えるとやる意味は無いと思います。
コメントありがとうございます。
説明書だと逆向きOKみたいに書いてあったと思うのですが、手元にないのでよくわかりません。
けどいろいろ話を聞く限り、狂っていく可能性が十分ありそうなので逆向きは使っていません。