先日書いた記事なんですが、

この件、結構前から何人かからコメントを貰ったりしていたんですが、毎回ソースも無いのでスルー気味でした。
何かそういうデータが出ているのかなと探していたんですが、ネタ元は見つけていたものの、データは見当たりません。
Contents
ボントレガーの主張
トレック傘下のボントレガーのタイヤでは、このように記されています。
ロードおよびグラベルタイヤは、大きくて太い方が速く転がること。同様のタイヤレイアップで見ると、履かせる向きで転がる速さが異なる場合がある。その差は場合によっては10%にもなるのだ。
タイヤを履かせる方向によって、最大10%も差が出るとの主張になっています。
私が知る限り、タイヤを履かせる方向は2パターンしかないと思うのですが、そこは皆さん同意ですよね?
特殊な履かせ方がある!と言われてもそれなりに困惑すると思います。
古タイヤをカットしてみましたが、トレッド層の中にあるケーシング層。

トレッド層だけ剥がそうと頑張ってみましたが、思っていたよりも難しいので省略。
転がり抵抗の9割はヒステリシスロス、つまりはタイヤが接地面で変形することによって起こるロスで、残りは摩擦によるロスもあると言われます。
ケーシング層の編み込みの方向性によって、ヒステリシスロスに影響を与える・・・のかは正直わかりません。
ですが全く影響しないとも言えないので、ここは評価が難しい。
ボントレガーが主張する最大10%というのも、10%となると結構大きい数字です。
ですがあくまでも最大値なんでしょうから、一般的なトップグレードのタイヤで平均してどれくらい差が出るのかなどは全く分かりません。
けど、私の記憶が正しければ、2014年ごろに愛用していたパナレーサーのRACE Aにはタイヤの方向の指定が無く、ツルツルスリックタイヤだったはず(現行品はわかりません)。
全く溝が無いスリックだったので気にしていなかったというのもありますが、たぶん今も回転方向の指定が無いタイヤってあるんじゃないですかね??
そういうのはメーカー的には向きは関係ないという判断なのかもしれないので、気にする必要もないのかと。
けど、ずいぶん前に使っていたヴィットリアのオープンコルサCX3とか、ヴィットリアのコルサとか、GP5000とかもそうですが、間違って逆向きに付けたところで転がりが悪いなという感想を持ったことはありません。
違いが分からない男だったというオチもあるかもしれませんが、個人的にはほぼ気にしていないポイントなので、最大10%と言われるとちょっと驚き。
タイヤの溝
車のタイヤであれば、溝は排水に関わる重要なところですが、ロードバイクのタイヤでは溝は排水に大きく関わらないと言われます。
それもあって、私自身は比較的テキトーにしていたのですが、あえて逆向きに履く理由も無いのは事実。


あえて逆につけるとグリップが増す
というのが良く効かれました
ただし、雨のレースでそれをやると
あっという間にグリップを失ってすっ飛んでいったらしいですが
MTBなどでリアタイヤだけ逆向きにしてグリップ力を上げるという話は聞いたことがありますが、ブロックタイヤであれば何となくイメージはつくものの、ロードタイヤではほぼ関係ないのかなと。
駆動輪のグリップを上げることで効率を上げるみたいな話だったと思いますが・・・
あと、突っ込むのを忘れていましたが、原付レースというものを初めて知りました。
実際のところ、タイヤメーカーが逆履きと正履きで転がり抵抗が違うというデータを持っているのかはわかりませんが、トレック(ボントレガー)の主張では最大10%違うこともあったとのこと。
私自身もやや懐疑的なんですが、もうちょっとタイヤを分解してケーシングの編み込みの方向性がどうなっているか見てみます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

![2本セット Continental(コンチネンタル) GRAND PRIX 5000 グランプリ5000 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51erAvOPApL._SL200_.jpg)
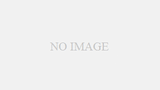

コメント
構造体のカーカスが対象に配置されているわけではないので、回転方向を守らないと過減速で荷重がかかった際に想定された変形にならずグリップが落ちたり抵抗が増えたり、またコンパウンド自体に方向性を持たせたものもあるらしいです。カーカスの継ぎ目の浮き上がり防止の予防的な意味もあります。自動車の場合ですが自転車も同じようなことかなと。
フレームを作るときはUDカーボンをどの向きに積層するかで性能が決まりますが、その方向を変えてしまう状態がタイヤの逆付けなのかな。
コメントありがとうございます。
結局のところ、タイヤメーカーは必ず方向性を持たせてカーカスを配置しているのか、特に気にしていないメーカーもあるのかについては全く分からなかったのですが、おっしゃるように、フレームのカーボンの配置が分かりやすいですね。
けどまあ、10%も変わるというのは結構大きな数字にも見えるし、ホンマかいな?というのが本音です。
配置については社外秘だと思うので、教えてくれないだろうと思いますが・・・
特に回転方向を定めていない場合は対称に配置してるので指定の必要が無いのかもしれません。あと、10%の差は何らかのピーク時だと思うので定速で流してる間はもっと小さいと思います。
なるほど。
確かに、ピークがどこにあるのか?という点を全く見逃してました。
ちょっと気になってGP5000を分解していたんですが、繊維に方向性がありそうな感じです。
カーカスの方向で変形の抵抗に異方性が生じるのを考えるのって、ちょいとタイヘン。静的なモデルではなくて、動的に考えないとハズしそう。
ただ、自転車のタイヤは自動車に比べると、内圧が高くて、マテリアルが少ないから、タイヤ自体の変形エネルギーって小さいのかも・・・
う〜ん、楽しい世界がありそうで、誰か解説してくれないかな〜
コメントありがとうございます。
ちょっと気になって調べてみたのですが、理論的にはあり得ると思いますが、詳細を解析するのは困難ではないかと・・・
ケーシングの繊維の交差角度が進行方向に向かって30度~45度程度まであるらしいので、それにより回転方向による差が出る可能性はあり得るとは思いますが・・・