以前から注目し何度も取り上げてきた「飲酒運転発覚回避のため事故後コンビニにブレスケアを買いに行った事件」。
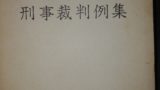
かなり複雑な経緯を経た裁判なので先にまとめておきます。
| 時期 | 出来事 |
| 2015/3 | 横断歩道で被害者をはねて死亡させた |
| <過失運転致死罪(自動車運転処罰法違反)> | |
| 2015/6 | 検察官は被告人を「過失運転致死罪」のみで起訴 |
| 2015/9 | 禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決(確定) |
| <速度超過罪(道路交通法違反)> | |
| 2018/2 | 速度超過罪で起訴 |
| 2019/3 | 手続き上の問題から公訴棄却(裁判の打ち切り) |
| <救護義務違反罪(道路交通法違反)> | |
| 2022/1 | 検察審査会の「不起訴不当」を受け、時効ギリギリに起訴 |
| 2022/11 | 長野地裁は救護義務違反の成立を認め懲役6月の実刑判決 |
| 2023/9 | 東京高裁が原判決を破棄し無罪に |
最高裁が弁論を開くのは原判決を破棄するサインな上、この件は事実認定に争いもなく道路交通法72条1項でいう「直ちに救護し」の解釈が争点でした。
予想通り最高裁は原判決を破棄し、救護義務違反の成立を認め有罪に。
事故から10年経過してから収監されるという異例な事態になりました。
Contents
救護義務の「直ちに」の解釈

問題になるのは「直ちに救護し」の「直ちに」とはどの範囲なのか?
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
※「直ちに」は「停止し」のみに掛かるわけではない。

さて、最高裁の判断をみていきましょう。
まずは事案の概要から。
第1 事案の概要
1 第1審判決が認定した犯罪事実の要旨は、「被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、長野県佐久市内の交通整理の行われていない交差点において、普通乗用自動車を運転中、被害者(当時15歳)に自車を衝突させて、同人を右前方約44.6m地点の歩道上にはね飛ばして転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたところ、その後すぐに車両の運転を停止したものの、直ちに救護措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。」というものである。2 第1審判決の認定及び記録によれば、本件の事実関係は次のとおりである。
⑴ 被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃(以下、時間のみを記載しているものは同日の時間である。)、長野県佐久市内において、普通乗用自動車を運転中、被害者に自車を衝突させ、同人を右前方約44.6m地点の歩道上にはね飛ばして転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こした。
⑵ 被告人は、フロントガラスがくもの巣状にひび割れたことから、自車を人に衝突させたと思い、衝突地点から約95.5m先で自車を停止させて降車し、衝突現場付近に向かった。
⑶ 被告人は、午後10時8分頃、衝突現場付近で靴や靴下を発見し、その後約3分間、付近を捜したが、被害者を発見することはできなかった。その間に、被告人は、通行人から救急車を呼んだかと聞かれたが、所持していた携帯電話で警察や消防に通報をすることはなかった。
⑷ 被告人は、午後10時11分頃、自車まで戻り、ハザードランプを点灯させた後、運転前に飲酒していたため酒臭を消すものを買おうと考え、自車の停止位置から、衝突現場とは反対方向にあり、約50.1mの距離にあるコンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入し、午後10時13分頃、これを摂取して、衝突現場方向に向かった。
⑸ その頃、通行人が、歩道上に倒れていた被害者を発見して、午後10時14分頃、110番通報をし、その通報がされている間に、被告人も、被害者の元に駆け寄って、人工呼吸をするなどした。
ここまでが事実認定。
次に一審と二審の判断。
第2 第1審判決及び原判決の要旨
1 第1審判決は、道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの。以下同じ。)72条1項前段、後段が救護義務及び報告義務を直ちに尽くすよう命じているのは、運転者が救護等の措置以外の行為に及ぶことによって救護等の措置を遅延させることは許されないという意味に解されるとした上で、被告人が、事故後すぐに衝突現場に戻ったものの、被害者を発見できないまま、警察官に飲酒運転の事実が発覚することを恐れて、コンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入、摂取するという、救護等の義務を尽くすことと対極の行動を優先させた時点で、救護義務及び報告義務の履行と相いれない状態に至ったとみるべきであり、それによって救護等の措置を遅延させたとして、直ちに救護等の措置を講じなかったと認め、被告人を懲役6月に処した。2 これに対し、被告人が控訴し、法令適用の誤り等を主張したところ、原判決は、被告人は事故後直ちに自車を停止させて被害者の捜索を開始しており、自車まで戻ってハザードランプを点灯させたことも危険防止義務を履行したものと評価でき、コンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入、摂取したことは、被害者の捜索や救護のための行為ではないものの、これらの行為に要した時間は1分余りで、そのための移動距離も50m程度にとどまっており、その後直ちに衝突現場方向に向かい、被害者が発見されると駆け寄って人工呼吸をするなどしていたことに照らすと、被告人は一貫して救護義務を履行する意思を保持し続けていたと認められ、このような事故後の被告人の行動を全体的に考察すると、人の生命、身体の一般的な保護という救護義務の目的の達成と相いれない状態に至ったとみることはできないとして、救護義務違反の罪の成立を否定した上で、第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、その場合、報告義務違反の点については既に公訴時効が完成しているとして、被告人に対して無罪を言い渡した。
一審と二審では「直ちに」についての評価が割れたことになる。
その上で最高裁は原判決を破棄し有罪に。
しかしながら、原判決の前記判断は是認することができない。その理由は、以下のとおりである。
1 道路交通法72条1項前段は、車両等の交通による事故の発生に際し、被害を受けた者の生命、身体、財産を保護するとともに、交通事故に基づく被害の拡大を防止するため、当該車両等の運転者その他の乗務員のとるべき応急の措置を定めたものである。このような同項前段の趣旨及び保護法益に照らすと、交通事故を起こした車両等の運転者が同項前段の義務を尽くしたというためには、直ちに車両等の運転を停止して、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護及び道路における危険防止等のため必要な措置を臨機に講ずることを要すると解するのが相当である。
2 前記第1の2の事実関係によれば、被告人は、被害者に重篤な傷害を負わせた可能性の高い交通事故を起こし、自車を停止させて被害者を捜したものの発見できなかったのであるから、引き続き被害者の発見、救護に向けた措置を講ずる必要があったといえるのに、これと無関係な買物のためにコンビニエンスストアに赴いており、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護等のため必要な措置を臨機に講じなかったものといえ、その時点で道路交通法72条1項前段の義務に違反したと認められる。原判決は、本件において、救護義務違反の罪が成立するためには救護義務の目的の達成と相いれない状態に至ったことが必要であるという解釈を前提として、被害者を発見できていない状況に応じてどのような措置を臨機に講ずることが求められていたかという観点からの具体的な検討を欠き、コンビニエンスストアに赴いた後の被告人の行動も含め全体的に考察した結果、救護義務違反の罪の成立を否定したものであり、このような原判決の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかで、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
最高裁判所第二小法廷 令和7年2月7日
東京高裁判決は、被害者を発見できなかった後の行動について以下のように捉えた。
◯東京高裁判決
原判決は、被告人は、ブレスケアを購入するために本件コンビニに赴いた時点で、交通事故を発生させた当事者として救護義務を「直ちに」尽くすことよりも、飲酒事実の発覚を回避するための行動を優先させており、そのような発覚回避行動に要した時間が二、三分間にとどまり、場所的にも数十メートル程度の離隔しかなかったとしても、交通事故を発生させた当事者が救護義務を尽くすことと、飲酒事実の発覚回避行動をとることは、内容や性質からみて対極の行動であり、前者より後者を優先させる意思決定を行動に移した時点で、前者の救護義務の履行と相容れない状態に至ったとみるべきであり、被告人は、上記発覚回避行動に及んだことにより救護の措置を遅延させたというべきであるから、「直ちに」救護の措置に及ばなかったという救護義務違反の罪が成立すると判断している。
しかし、飲酒事実の発覚を回避する意思は、道義的には非難されるべきものであるとしても(もっとも、被告人が身体に保有していたアルコール量は、酒気帯び運転の罪を構成する程度に達していなかった。)、救護義務を履行する意思とは両立するものであって背反するものではなく、上記発覚回避行動に出たからといって救護義務を履行する意思が否定されるものではないから、被告人が同意思を失ったとは認められない。前記2のとおり、被告人は、救護義務を履行する意思の下に直ちに被告人車両を停止して被害者の捜索を開始し、被害者が発見された後は実際に救護措置を講じており、その間に捜索や救護のためではない上記発覚回避行動に出ているものの、本件事故後の被告人の行動を総合的に考慮すれば、人の生命、身体の一般的な保護という救護義務の目的の達成と相容れない状態に至ったとみることはできない。原判決は、救護義務違反の罪が成立するかどうかは、当該事案全体を見渡し、様々な事情を総合的に考慮して判断すべきであると説示するものの、本件事故後における救護義務を履行する一貫した意思の下での被告人の行動の全体的な考察を十分に行わず、飲酒事実の発覚回避という行為の目的を過度に重視した結果、救護義務違反の罪の構成要件への当てはめを誤ったものといわざるを得ず、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。
4 検察官の主張について
検察官は、法令用語としての「直ちに」は、即時性が強く一切の遅滞を許さないとされていることなどからすれば、道路交通法72条1項前段の「直ちに」とは、事故発生の後、無為のうちに時間を空費したり、法が命じる救護の措置以外の一切の行為を行うことを許さない趣旨と解すべきであり、これと同様の解釈に基づき、被告人に救護義務違反の罪が成立するとした原判決の判断は正当である旨主張する。
しかし、原判決は、前記3のとおり、救護義務違反の罪が成立するには、当該事案全体を見渡し、事案全体に表れた様々な事情を総合的に考慮して、救護義務の履行と相容れない状態に至ったといえる必要があることを前提に同罪の成否について判断しており、救護の措置以外の行為をしたら直ちに同罪が成立するとの解釈を採っているものとは解されない。検察官の上記主張は採用できない。
また、検察官は、原判決は、被害者の捜索活動と並行して119番通報を行うことが可能であったのにそれをしなかったなどの不作為を問題視し、ブレスケアの購入、服用という逸脱行動に及んだ段階で、期待された措置を講じなかったという不作為が可罰的な程度に達したとして、救護義務違反の罪が成立すると認定したものと解され、かかる原判決の判断は正当であるとも主張する。しかし、被害者が発見されていないため、119番通報をすることよりも被害者を捜索、発見して救護措置を講じることを優先したからといって、人の生命、身体の保護という救護義務の目的に直ちに反することになるとはいえないし、被害者が発見されていない状況で119番通報をしたとしも、被害者の所在や負傷状況等を救急隊員に伝えることができず、被害者の救護に直ちにつながらないから、本件において、被告人が119番通報をしなかったことを重視して救護義務違反の罪の成立を認めることはできないというべきである。検察官の上記主張も採用できない。
5 以上によれば、被告人に救護義務違反の罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、その余の控訴趣意について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、原判決は、救護義務違反の罪と報告義務違反の罪とが科刑上一罪の関係にあるものとして1個の判決をしているから、結局、原判決は全部破棄を免れない。
東京高裁 令和5年9月28日
東京高裁は被害者を発見できなかった状況においても、被告人が救護履行する意思を保持していたと捉えた。
しかし最高裁は被害者を発見できなかった状況においても、フロントガラスが大破して事故発生を認識した以上は引き続き被害者の捜索にあたることが救護義務の履行と解釈した。
そして引き続き被害者の捜索にあたるべきなのに、救護義務とは無関係な「コンビニにブレスケアを買いに行った」ことが救護義務違反に該当すると判断。
この評価は以前から指摘しているように真っ当でしょう。
東京高裁判決は「直ちに」と規定している趣旨を蔑ろにしていたのだから。
若干気になるとしたらここ。
原判決は、本件において、救護義務違反の罪が成立するためには救護義務の目的の達成と相いれない状態に至ったことが必要であるという解釈を前提として、被害者を発見できていない状況に応じてどのような措置を臨機に講ずることが求められていたかという観点からの具体的な検討を欠き、コンビニエンスストアに赴いた後の被告人の行動も含め全体的に考察した結果、救護義務違反の罪の成立を否定したものであり、このような原判決の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり
「救護義務違反の成立には救護義務の達成と相容れない行動をとれば即ち救護義務違反ではなく、一定の時間的空間的な離隔を必要とする」、としたのは東京高裁 平成29年4月12日判決ですが、
救護義務及び報告義務の履行と相容れない行動を取れば、直ちにそれらの義務に違反する不作為があったものとまではいえないのであって、一定の時間的場所的離隔を生じさせて、これらの義務の履行と相容れない状態にまで至ったことを要する
東京高裁 平成29年4月12日
そもそもこの概念をベースにした原判決の前提を否定しているようにもとれる。
そうなると今後の救護義務違反に影響するようにもみえますが、今回の事例をみると「直ちに」について最高裁が説示したわけではなくあくまでも今回の事例のように被害者を発見できなかった後の行動について判断しただけにも見える。
当たり前といえば当たり前

「直ちに救護し」とある以上、コンビニにブレスケアを買いに行き「飲酒運転発覚回避行動」をとることが救護義務違反だと捉えるのはごく自然。
むしろ東京高裁 平成29年4月12日判決以降の流れを牽制したかのようにも見える。
ところで今回の事案、事故から約10年経過し、過失運転致死罪の執行猶予期間も既に終了した後に被告人が収監されることになる。
そもそもこの事案については、被告人の運転行為と救護義務違反がまず非難されるのは当然としても、次に非難されるべきなのは過失運転致死罪と救護義務違反を併合罪として起訴しなかった検察官なのよ。
ざっくりいえば、救護義務違反が無罪になりうるからとヒヨって過失運転致死罪のみで起訴したわけで。
検察官は少しでも無罪になるリスクがある事案について勝負しないことが通常で、だから有罪率99%以上という高率になる。
しかし被害者遺族がこの10年間経験してきたことを考えても、最初から過失運転致死罪と救護義務違反の両方で起訴すべきだった。
検察官の主張が認められて良かったね、で済ますのも問題なのではなかろうか?
それと同時に東京高裁がおかしな解釈を持ち出したことを最高裁が否定しただけでもあるので、本来あるべき救護義務に正しただけなのかも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント