この人が判例を扱うと、なぜか内容が改竄されてしまう問題がありますが、



今度は最高裁が示した信頼の原則(最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月13日)の解説をしている。
被告人は交通法規に則り適切な右折方法を採ったのだと繰り返し解説してますが、判決文を読んでいたならそのような解説にはならないのよね…
最高裁が示した信頼の原則
この事案は過去に取り上げてますが、事案の概要はこう。

被告人は、原動機付自転車の運転業務に従事するものであるところ、昭和39年4月27日のいまだ灯火の必要がない午後6時25分ごろ、第一種原動機付自転車を運転して、京都市a区b通を南進し、幅員約10メートルの一直線で見通しがよく、他に往来する車両のない同区c上るd町e番地先路上において、進路の右側にある幅員約2メートルの小路にはいるため、センターラインより若干左側を、右折の合図をしながら時速約20キロメートルで南進し、右折を始めたが、その際、右後方を瞥見しただけで、安全を十分確認しなかつたため、被告人の右後方約15メートルないし17.5メートルを、第二種原動機付自転車を時速約60キロメートルないし70キロメートルの高速度で運転して南進し、被告人を追抜こうとしていたA(当時20年)を発見せず、危険はないものと軽信して右折し、センターラインを越えて斜めに約2メートル進行した地点で、同人をして、その自転車の左側を被告人の自転車の右側のペタルに接触させて転倒させ、よつて、翌28日に、同人を頭部外傷等により死亡するに至らせたものである。
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月13日
被告人は第一種原付を運転し、いわゆる小回り右折をした。
後続車(第二種原付)はセンターラインを越えて、しかも時速60~70キロで被告人を追い越ししようとし接触。
後続車の運転者が死亡した事案です。
これについて原判決は、被害者の無謀な運転が事故の主たる原因だと認めた上で、被告人の右折時安全確認に問題があるとして有罪にしている。
したがつて、Aとしては、右法規に従い、速度をおとして被告人の自転車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行しなければならなかつたものといわなければならない。しかも、右距離は、このような行動に出るために十分なものと認められる。しかるに、Aは、時速約六〇キロメートルないし七〇キロメートルの高速度で、右折しようとしている被告人の右側から、被告人の自転車を追越そうとして、すでにセンターラインを越えて約二メートルも斜め右に進行している被告人の自転車の右側に進出し、これと接触したというのであるから、Aの右追越し(原判決は、Aは、被告人を追抜こうとしたものであつて、追越しをしようとしたものではないとしているが、Aは、右のとおり、センターラインを越えた被告人の右側に進出し、その前方に出ようとしていたのであるから、むしろ追越しに当るものとみるのが相当である。)は、交通法規を無視した暴挙というほかはなく、これが本件衝突事故の主たる原因になつていることは、原判決も認めるところである。
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月13日
刑事では被害者の違反があったとしても被告人に過失があれば有罪になりますが、最高裁は信頼の原則を採用し被告人に過度な注意義務を課すことを牽制した。
被告人は、進路右側にある小路にはいるため、原判示のように、センターラインより若干左側を、右折の合図をしながら時速約20キロメートルで南進し、右折を始めたというのであるから、その後方にある車両は、被告人の自転車の進路を妨げてはならないのである(本件当時の道路交通法34条4項参照)。また、このような状態にある被告人の自転車を追越し、もしくは追抜こうとする車両は、被告人の自転車の速度および進路に応じて、できるだけ安全な速度と方法で進行しなければならない(同28条3項参照)のみらず、本件現場は、センターラインの左側の部分が約5メートルあるのであるから、センターラインの右側にはみ出して進行することは許されないわけである(同17条4項参照)。ところで、被害者Aは、被告人が右折を始めた当時、その十数メートル後方にいたのであるから、被告人の動向、ことに被告人が右折しようとしているものであることを十分認識しえたはずである。
したがつて、Aとしては、右法規に従い、速度をおとして被告人の自転車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行しなければならなかつたものといわなければならない。しかも、右距離は、このような行動に出るために十分なものと認められる。しかるに、Aは、時速約60キロメートルないし70キロメートルの高速度で、右折しようとしている被告人の右側から、被告人の自転車を追越そうとして、すでにセンターラインを越えて約2メートルも斜め右に進行している被告人の自転車の右側に進出し、これと接触したというのであるから、Aの右追越し(原判決は、Aは、被告人を追抜こうとしたものであつて、追越しをしようとしたものではないとしているが、Aは、右のとおり、センターラインを越えた被告人の右側に進出し、その前方に出ようとしていたのであるから、むしろ追越しに当るものとみるのが相当である。)は、交通法規を無視した暴挙というほかはなく、これが本件衝突事故の主たる原因になつていることは、原判決も認めるところである。
ところで、車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。
このようにみてくると、本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月13日
で。
運転レベル向上委員会の中の人は「被告人は交通法規に違反せずきちんと右折した」と解説してますが、判決文を読んでいたならそのような解説にはなり得ない。
なぜなら当時、第一種原付の右折方法は小回り右折ではなくいわゆる二段階右折だから。
当時のルールはこれ。

○昭和39年改正以前の34条3項
第三十四条
3 第一種原動機付自転車又は軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
※第一種原付はジュネーブ条約との兼ね合いで、昭和39年改正で二段階右折⇒小回り右折に変更された。
原審は被告人の右折方法違反と後方安全確認義務を肯定したものの、最高裁は右折方法違反と注意義務は無関係だとした。
なお、本件当時の道路交通法34条3項によると、第一種原動機付自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならなかつたのにかかわらず、被告人は、第一種原動機付自転車を運転して、センターラインの若干左側からそのまま右折を始めたのであるから、これが同条項に違反し、同121条1項5号の罪を構成するものであることはいうまでもないが、このことは、右注意義務の存否とは関係のないことである。
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月13日
これの意味をどう考えるかですが、正規の右折方法(二段階右折)をしようとも結局後方安全確認をしないとこの事故は回避できない。
最高裁が示したのは「右折時の後方確認義務の範囲」でして、センターラインを越え高速度で追い越しする後続車を予見する注意義務はないとした一方、それとは別に被告人の右折方法違反(34条3項、121条1項5号)は成立するとしている。
右折方法違反と事故に因果関係がないとしたわけ。

ところで、判決文にもあるように被告人の右折方法違反は明らかなところ、なぜ運転レベル向上委員会の人は判決内容を改竄したのだろうか?
判決文を読まずに解説しているのか、判決文の意味を理解できなかったのかはわからない。
ただまあ、この人は違反と過失の区別がついてないので、正しい内容を解説すると過去動画で解説してきた内容と矛盾してしまうのと、そもそも過失致死の成立要件を理解してないことが根底にあると思う。
内容の改竄はマスコミでもご法度ですが、なぜこの人は事実をねじ曲げて解説するのかわからないのよね。
さらに気になる点としては、この人は判決年月日を解説する動画と、なぜか判決年月日を伏せている動画がある。
判決年月日を伏せた動画について明らかに事実と異なる解説が散見されているのを考えると、判決文を調べられたくない事情があるのか?と勘ぐってしまうのよ。
法律解釈についても明らかな間違いがかなりありますが、判決内容を改竄してこの人は何をしたいのかわからない。
なおイエローのセンターライン(はみ出し追い越し禁止)があったのかわからないみたいな解説をしてますが、ちょっと考えればわかるんだけどはみ出し追い越し禁止規制があった可能性は0%です。
理由はあえて書きませんが。
そもそも被告人側が求めていたもの

この事件は被告人が時速20キロで右折を開始した際に、被害者は被告人の後方15~17.5mという至近距離にいたという認定になっていて、この事実関係では原審が「後方安全確認不足」を指摘した理由もわかる。
その上で被告人が上告した狙いはなんだったのでしょうか?
それは上告趣意に理由がある。
判例違反
被告人が上告した理由は、原判決が名古屋高裁金沢支部 昭和40年8月7日判決と東京高裁 昭和38年7月17日判決に違背するというもの。
どちらも要約すると「右折する際に50m以上後方にいる後続車を確認する注意義務はない」。
左折又は右折しようとする車両が、それぞれ道路の左側又は中央に寄ろうとして方向指示器による合図をしたときは、その後方にある車両は、当該合図をした車両の進行を妨げてはならないのであつて(道路交通法34条5項)、一般に道路を通行する者は、特段の事情のない限り、他の通行者がこのような基本的な交通規則は、これを守ることを前提として、歩行し、あるいは車両を運転しているのであり、さもないと道路の交通は、たちまち渋滞し、その安全と円滑は、とうてい、これを期しがたい。まして本件の場合、後続車である前記Aは約50mないし60m後方にあつたのであるから、右距離関係から被告人が右Aの前方を安全に右折し得るものと信じたのは、まことに無理からぬところといわねばならない。原判決は更に、当時右Aは50キロないし60キロの時速で進行して来たのであるから、3秒余りで被告人の停車地点に到達し得ると説示しているが、50mないし60m離れた地点を走行する車両の速度を肉眼で確認することは至難のことと解されるのであつて、とつさの間に右二輪車の速度を看取し、被告人の停車地点に到達するまでの時間を逆算して衝突の危険がある場合には右Aを通過させた後発進すべきであつたとする原判決は、これ又被告人に難きを求めるものといわねばならない。これを要するに、原判決がその認定した具体的状況の下で被告人の注意義務の内容として説示するところは、自動車運転者に一般的に要求される程度を超えたものである。本件事故の原因は、すべて右Aの違法、無謀な運転に帰せらるべきであり被告人に過失は認められない。従つて被告人に過失責任を認めた原判決には事実を誤認したか、または法律の解釈、適用を誤つた違法があり、右は判決に影響を及ぼすことが明かであるから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
名古屋高裁金沢支部 昭和40年8月7日
ところが今回の事案は、被告人が右折を開始した際の距離は15~17.5m。
つまり事案が違う判例を引用したかにみえますが、その先がある。
事実誤認

原審の事実認定によると、被告人は右折開始して衝突地点までの5mの距離を時速20キロで走行した(その間0.9秒)としており、被害者が時速60~70キロとしたら右折開始時の両者の距離は15~17.5mになる。
しかし被告人の主張は、「時速20キロではなく歩いているのと変わらない速度」だったと主張。
この根拠としては、被告人は衝突の瞬間に左にハンドルを切り転倒しなかったこと等を挙げている。
歩く程度の速さだから咄嗟にハンドルを切り転倒しなかったとし、仮に被告人の速度が時速6キロだとすると5m走行するのに要するのは3秒。
その前提で右折開始時の被害者の位置を計算すると、時速60~70キロの被害者は被告人の後方65.13~75.66mにいたことになり、名古屋高裁金沢支部判決や東京高裁判決に違背すると主張。
被害者の違反

そして被害者は安全運転義務違反(70条)、左側通行義務違反(当時17条3項)、速度超過(22条)、合図車妨害(当時34条5項)に違反していたことから、被害者の無謀な運転が原因だと主張。
民事への影響

当時被告人は被害者から損害賠償請求訴訟を提訴されていて、刑事判決が民事に影響しかねないことも主張。
民事と刑事では過失の認定が違うのであまり意味がない主張にも思えるけど、おそらくは事実認定を何とか変えたかったのではないかと思う。
被告人が「歩く程度の速さ」で右折したのであれば、被害者はかなり後方にいたことになりますが、刑事の事実認定と民事の事実認定が必ずしも一致しないにしても刑事で「20キロで右折」と認定されたままだと不利になる。
なお、民事と刑事で事実認定が違うケースはわりと普通。
所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ、原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく、また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。
最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日
これらからすると、被告人の狙いは民事を見据えたものだったのだと理解できますが、刑事で信頼の原則が認められたとしても民事に適用されるかはビミョー。
それを考えると、被告人は「事実認定を見直した上で破棄して欲しかった」のかなと思う。
仮に時速6キロ程度で右折したという認定なら、民事でもそれが採用されたら被告人に有利に働きますから…
危惧するのは


この人の主張内容って「右折方法に問題なかったのに、下級審が有罪認定した」ことを非難しているようにも取れますが、この事案は「右折方法が法規に反していた事案」。
全然違う内容にし結果として謎の印象操作になってますが、そもそも最高裁が信頼の原則を認めたのは昭和41年12月20日判決と言われており、まだ確立された考え方とも言い難い状況だった。
最高裁が信頼の原則を認めて以降、下級審でも信頼の原則が乱発して「信頼の原則をやりすぎた」と思われる判例もありますが、

右折方法が法規に反していたことや当時まだ信頼の原則が確立されていたとも言い難い状況では下級審の判断はむしろ正論だったとも言えて、最高裁は当時の過失犯の注意義務に制限を掛けたことになる。
判決を違う内容に改竄するのは論外ですが、事実をきちんと扱わない彼のスタンスを如実に表した動画なのかもしれません。
ちなみに刑事無罪と民事無過失は別なので、無罪を勝ち取ったとしても民事でこの認定なら無過失はムリ。
右折開始時にはるか後方にいたというなら、民事でも被害者の一方的な過失とみなされる可能性はありますが、何せ至近距離だった認定なので…
ただまあ、仮に同じ事故を自転車が起こしたとしたら、

「ちゃんと二段階右折しなかった自転車が悪い」という世論になるのは目に見えている。
あくまでこの事故は「当時の法律に反し二段階右折しなかった原付が起こした事故」ですが、彼はなぜ「右折方法に問題なかった」と虚偽の解説をするのかさっぱりわからないのよね。
何度も明らかな間違いを披露している様子をみると、わざわざ虚偽の内容にするのは何の目的があるのかわからない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
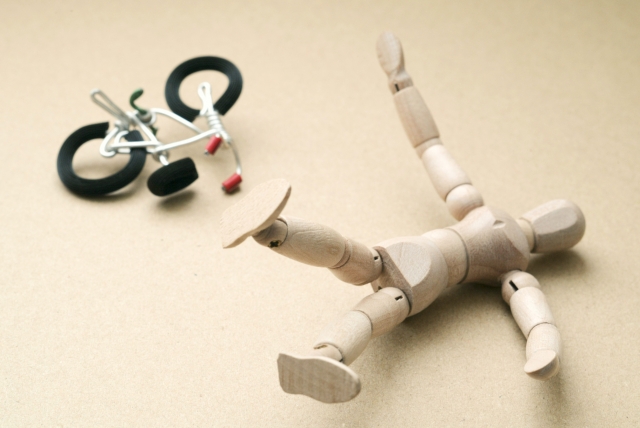


コメント